SC経営士試験2024商業一般問題と解答【第1問】【第2問】【第3問】
解答1から20まで、問題、解答はSC協会のHPから作成しています。問題の最後に用語の意味も記載しています。略語にはいくつかの意味がありますので、ご自分でも調べてください。
https://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html
一部AIによる解説も入れていますが、参考程度にご利用ください。
小売業のサステイナビリティ
【第1問】〈配点 10点〉 (解答番号は 1 から 5 ) 小売業のサステイナビリティに関する次の文章を読み、文中の空欄に最も適切な語句を下記のそれぞれの語群 から選び、その番号をマークしなさい。
プラスチック資源循環促進法
2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」は、プラスチックの資源循環を進めて持続可能な社 会を実現することを目的とした法律である。この法律により、事業者は製品の設計・製造、販売・提供、排出・ 回収のすべての段階において資源循環への配慮が求められる。こうした取り組みを通して、廃棄物の発生を少 なくするリデュースやリサイクルなど従来の「3R」や、原料の再生可能資源への代替を意味する「 1 」 が促進され、「大量生産・大量消費・大量廃棄」に代わる 2 への移行が進むと期待されている。
プラスチックに代わる環境に配慮した素材が求められるなか、石灰石を主原料とする「 3 」への注 目が高まっている。「 3 」は、炭酸カルシウムなど無機物を50%以上含んでおり、プラスチック成分 を大幅に削減できる。主原料の石灰石は日本でも自給率が高く安定して入手できるほか、使用することで二酸 化炭素の排出がどのくらい削減されるのかを数値化することができる。使い終わった「 3 」を製品原 料として再資源化する 4 が可能な点もメリットという。
アパレル業界ではファストファッションが台頭しはじめた2000年ごろから、商品の過剰供給の傾向が強まり、 多くの企業で余剰在庫が課題となっている。生活者の消費への意識も変化し、アパレル業界においてもサステ イナブルであることが重視され、余剰在庫の問題解決に目が向けられている。こうした課題の解決に向けた取 り組みとして、環境負荷に配慮した新素材や、捨てられる製品に新たな価値を付加して再生する 5 も 注目されている。
語群
1 1.Refuse 2.Return 3.Renewable 4.Reuse 5.Repair
5R(サステイナブルな消費行動)
- Refuse(リフューズ)
不要なものは「断る」。例えば、使い捨てのレジ袋やストローを断るなど。 - Return(リターン)
使い終わった製品や容器を返却すること。リサイクルや再利用のために回収される。 - Renewable(リニューアブル)
再生可能な資源やエネルギーを使うこと。太陽光や風力など。 - Reuse(リユース)
物を繰り返し使うこと。たとえば、瓶や服を別の用途で使うなど。 - Repair(リペア)
壊れた物を修理して使い続けること。廃棄を防ぎ、資源を節約する。
2 1.カーボンエコノミー 2.サーキュラーエコノミー 3.リニアエコノミー 4.サーマルエコノミー 5.水平エコノミー
経済モデルの用語
- カーボンエコノミー
二酸化炭素(CO₂)排出の削減を重視する経済活動。脱炭素社会を目指す。 - サーキュラーエコノミー
「循環型経済」。資源を無駄にせず、再利用・リサイクルする経済モデル。 - リニアエコノミー
「直線型経済」。資源を取って使い、使い終わったら捨てる従来のモデル。 - サーマルエコノミー
廃棄物を燃やして熱エネルギーとして利用する経済活動。 - 水平エコノミー
同じ用途のままで資源を再利用するモデル(例:ペットボトルから新しいペットボトルを作る)。
3 1.COP 2.FIT 3.ZEB 4.LIMEX 5.GX
環境・技術に関する用語
- COP(Conference of the Parties)
気候変動に関する国連会議。温暖化対策など国際的なルールを議論する。 - FIT(Feed-in Tariff)
再生可能エネルギーで発電した電力を、一定価格で買い取る制度。 - ZEB(Zero Energy Building)
使うエネルギー量と作るエネルギー量が同じ建物。エネルギーの自給自足を目指す。 - LIMEX(ライメックス)
石灰石から作られる新素材。紙やプラスチックの代替として注目される。 - GX(グリーントランスフォーメーション)
環境に優しい社会や産業へと転換する動き。脱炭素や再エネ導入など。
4 1.アップサイクル 2.ケミカルリサイクル 3.サーマルリサイクル 4.ダウンサイクル 5.マテリアルリサイクル
リサイクルの種類
- アップサイクル
不要な物を、元より価値の高い物に加工する。例:古着をバッグに変える。 - ケミカルリサイクル
化学的に分解し、原料として再利用する方法。プラスチックの再資源化など。 - サーマルリサイクル
ごみを燃やして熱エネルギーとして利用する方法。 - ダウンサイクル
リサイクルによって価値が下がる再利用。例:古紙を再生紙にするなど。 - マテリアルリサイクル
素材として再利用する方法。プラスチックや金属の再加工など。
5 1.リメイク 2.アップサイクル 3.ダウンサイクル 4.リユース 5.リセール
再利用に関する用語
- リメイク
古い物をデザインや用途を変えて新しく作り直すこと。 - アップサイクル
価値を高めて再利用(上記参照)。 - ダウンサイクル
価値が下がっても再利用(上記参照)。 - リユース
そのまま、もしくは少しだけ手を加えて繰り返し使う。 - リセール
中古品として再び販売すること。フリマや中古ショップなどが例。
小売業
【第2問】〈配点 10点〉 (解答番号は 6 から 15 ) 小売業に関する以下の記述のうち正しいものには1を、誤っているものには2を、解答欄にマークしなさい。
商業動態統計調査 2023年の小売業販売額
6 経済産業省「商業動態統計調査」によると、2023年の小売業販売額は、すべての業種で対前年を上 回った。
2
【誤り(2)】
解説:
2023年の小売業全体では前年より販売額が増加した業種が多いですが、「すべての業種」で上回ったわけではありません。一部業種では販売額が前年を下回っているため、「すべての業種」が誤りです。
小売業の中で最も販売額が大きい業態
7 経済産業省「商業動態統計調査」によると、2023年の小売業販売額のうち主要業態のなかで最も販 売額が大きいのはコンビニエンスストアである。
2
【誤り(2)】
解説:
小売業の中で最も販売額が大きい業態は 「スーパーマーケット」 です。コンビニエンスストアも大きな業態ですが、販売額ではスーパーマーケットのほうが上です。
2023年百貨店販売額
8 経済産業省「商業動態統計調査」によると、2023年百貨店販売額のうち、「飲食料品」の販売額は「紳 士服・洋品」「婦人・子供服・洋品」をあわせた販売額よりも大きい。
1
【正しい(1)】
解説:
2023年の百貨店において、「飲食料品」の販売額は「紳士服・洋品」「婦人・子供服・洋品」を合わせた額よりも大きくなっています。これはコロナ禍以降、食料品への需要が高まったことが背景にあります。
コンビニエンスストア業界
9 コンビニエンスストア業界では、コンビニエンスストアにスーパーマーケットの要素を加えた店舗 の開発の動きがみられる。たとえばファミリーマートは「SIPストア」を実験店として出店した。
2
【誤り(2)】
解説:
ファミリーマートが展開している実験店は「次世代CVS実験店舗」で、「SIPストア」という名称ではありません。「SIP」は別の文脈(たとえば官民連携の研究プロジェクト名など)で使われる用語です。
大規模小売店舗立地法の新設届出件数
10 「SC JAPAN TODAY」によると、大規模小売店舗立地法の新設届出件数は、2021年度、 2022年度は600件台であったが、2023年度は600件を下回った。
1
【正しい(1)】
解説:
「SC JAPAN TODAY」によれば、大規模小売店舗立地法に基づく新設届出件数は2023年度に600件を下回ったことが確認されています。2021年度・2022年度は600件台でした。
第7回地域貢献大賞
11 第7回地域貢献大賞を受賞したSCは「SAKURA MACHI Kumamoto(サクラマチ クマモト)」であり、国土交通省都市局長賞をあわせて受賞した。
1
【正しい(1)】
解説:
「SAKURA MACHI Kumamoto(サクラマチクマモト)」は第7回地域貢献大賞を受賞しており、さらに国土交通省都市局長賞もあわせて受賞しています。地域貢献と都市開発の両面で評価された施設です。
電子商取引に関する市場調査
12 経済産業省2022年度「電子商取引に関する市場調査」によると、物販系分野、サービス系分野、デジ タル系分野いずれもBtoC-EC市場規模は対前年で増加している。
2
【誤り(2)】
解説:
「電子商取引に関する市場調査」(2022年度版)によれば、「サービス系分野」は前年と比べて市場規模が減少しました。よって、「すべての分野で増加」というのは誤りです。
2024年問題
13 「2024年問題」のなかで物流の効率化が求められるが、大規模かつ郊外にある物流センターから配 送する仕組みを「マイクロ・フルフィルメント」という。
2
【誤り(2)】
解説:
「マイクロ・フルフィルメント」は都市部や近郊に小型の物流拠点を設けて、短時間配送を実現する仕組みです。「大規模かつ郊外の物流センター」とは逆の意味になるため、誤りです。
エコデザイン規制
14 米国では、環境に配慮した商品の設計を義務づける「エコデザイン規制」が制定された。これによっ て域内で事業展開するアパレル事業者に対し、売れ残った衣料品の廃棄が禁止されることになる。
2
【誤り(2)】
解説:
「エコデザイン規制」は**EU(欧州連合)**において進められている規制であり、米国ではありません。また、「売れ残った衣料品の廃棄禁止」も欧州での動きです。
RFM分析
15 いつ買ったか、どのくらいの頻度で買っているか、いくら使っているかに関するデータをもとに、 優良顧客のセグメンテーションを行う分析手法をRFM分析という。
1
【正しい(1)】
解説:
**RFM分析(Recency, Frequency, Monetary)**は、以下の3つの指標で顧客を分類する分析手法です:
- Recency(最近の購入日)
- Frequency(購入頻度)
- Monetary(購入金額)
この分析を使って、優良顧客のセグメンテーションが可能になります。
小売業に関連する用語
【第3問】〈配点 10 点〉 (解答番号は 16 から 20 ) 次の文章は、小売業に関連する用語についての記述である。記述文と最も関連の深い語句をそれぞれの語群 から選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
ストアコンパリゾン
16 競合する店を品揃えや価格、売場のレイアウト、接客サービスや販売促進など、さまざまな角度から比較考察し、自社や自店の経営に役立てること。
語群 16 1.CLT 2.ストアポジショニング 3.ミステリーショッパー 4.LEED 5.ストアコンパリゾン
1.CLT(Cross Laminated Timber)|直交集成板
- 意味: 木材を繊維方向が直交するように何層にも重ねて接着した構造用パネル。
- 用途: 建築材料として使用され、高層建築物や商業施設の環境配慮型構造材として注目されています。
- サステイナビリティの視点: 木材は再生可能資源であり、CLTは**脱炭素建築(カーボンニュートラル)**の一環として推進されています。
2.ストアポジショニング(Store Positioning)
- 意味: ある小売店舗が市場の中で、どのようなイメージや役割を持って顧客に認識されるかを明確にする戦略。
- 例: 「高品質・高価格の高級志向スーパー」や「安さ重視のディスカウントストア」など。
- 目的: 他店との差別化やターゲット顧客への訴求力を高め、ブランディングにつなげる。
3.ミステリーショッパー(Mystery Shopper)|覆面調査員
- 意味: 一般客を装って店舗を訪れ、サービスや接客、清掃状況などをチェック・評価する人のこと。
- 活用目的:
- 店舗スタッフの接客レベルの把握
- 顧客満足度の向上
- 現場の問題点の発見
- メリット: 客観的でリアルな現場の評価が得られる。
4.LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)
- 意味: アメリカのグリーンビルディング協会が策定した、建物の環境性能を評価・認証する国際的な制度。
- 評価項目: 省エネ、資源効率、室内環境の質、持続可能な敷地開発など。
- 関連性: 小売店舗やSCがLEED認証を取得することで、環境配慮型施設としての信頼性を高めることができる。
5.ストアコンパリゾン(Store Comparison)|店舗比較調査
- 意味: 自社と他社(競合)店舗を比較して、売場づくり・商品構成・価格・サービスなどを分析する手法。
- 活用例:
- ベンチマーキング(他社の優れた点を学ぶ)
- 改善点の洗い出し
- 新店計画時の市場調査
- ポイント: 客観的に比較し、競争優位性のある戦略を立てる材料となる。
バスケット分析
17 POS等のデータから、一緒に買われている商品の組み合わせを明らかにする分析手法。
語群 17 1.クラスター分析 2.バスケット分析 3.コンジョイント分析 4.コレスポンデンス分析 5.POS分析
1.クラスター分析(Cluster Analysis)
- 意味: 類似した特徴を持つデータをグループ(クラスター)に分類する手法。
- 小売業での使い方:
- 顧客のタイプ分け(セグメント):年齢・購買履歴・購入金額などから、似た傾向の顧客グループを抽出。
- それぞれのグループに適した販促や商品展開ができる。
- 例: 「まとめ買いする主婦層」「頻繁に少額購入する学生層」などに分類。
2.バスケット分析(Basket Analysis)
- 意味: 一緒に購入されやすい商品を分析する手法。正式には「アソシエーション分析(関連ルール分析)」とも呼ばれます。
- 小売業での使い方:
- レジで一緒に買われた商品データから、「商品Aを買った人は商品Bも買う傾向がある」といった**関連性(ルール)**を導き出す。
- 例:
- おにぎりを買った人は、ペットボトルのお茶も一緒に買うことが多い → 並べて陳列する
- おむつとビールの組み合わせ(有名な事例)
3.コンジョイント分析(Conjoint Analysis)
- 意味: 商品やサービスにおいて、どの要素(価格・デザイン・機能など)が顧客にとって重要かを明らかにする手法。
- 小売業での使い方:
- 新商品の開発、パッケージデザインの決定、価格帯の検討など。
- 例: 顧客が「低価格」「ブランド」「機能性」のどれを重視して商品を選んでいるかを数値的に分析。
4.コレスポンデンス分析(Correspondence Analysis)
- 意味: クロス集計表(2つのカテゴリー間の関係)を視覚的に表現する多変量解析手法。
- 小売業での使い方:
- 商品カテゴリと顧客層(年齢・性別など)との関係性を視覚化して理解。
- 例: 「若年層はスナック菓子を好む」「中高年は健康食品を購入しがち」といった傾向を図で表示できる。
5.POS分析(Point of Sale Analysis)
- 意味: POSレジで記録された販売データ(購入商品・時間・金額・数量など)を活用して、販売状況を分析する手法。
- 小売業での使い方:
- 売れ筋・死に筋商品の把握
- 販売時間帯や曜日別の傾向分析
- 効果的なプロモーション施策立案
- 例:「水曜日はパスタソースの売上が伸びる」→ チラシに掲載する。
これらの手法は、データを活用して売上の最大化・顧客満足の向上・商品戦略の最適化などに役立つ、マーケティングの重要な武器です。
PI値
18 ある商品のレジ通過客数1,000人あたりの売上金額や販売数。スーパーマーケットなどで、商品の 売上金額や販売数を予測する際に使用される。
語群 18 1.PI値 2.リフト値 3.NPS 4.ノーム値 5.CVR
1.PI値(Purchase Index|購買指数)
- 意味: 来店客のうち、ある商品を購入した人の割合を示す指標。
- 計算式:
購入者数 ÷ 来店客数 × 100(%) - 小売での使い方:
「どの商品がよく買われているか」「どの棚が効果的か」を知るために使います。
たとえば、同じ来店数でもPI値が高い=その商品は魅力的ということ。
2.リフト値(Lift Value)
- 意味: 「商品Aを買った人が、商品Bも買う確率がどれくらい高いか」を示す指標。
- バスケット分析でよく使われる。
- 目安:
- リフト値 > 1: 一緒に買われやすい(強い関連)
- リフト値 = 1: 関連性なし
- リフト値 < 1: 一緒に買われにくい
- 活用例:
「パンと牛乳」「カレーと福神漬け」など、一緒に売ると効果的な組み合わせが見つかる。
3.NPS(Net Promoter Score)
- 意味: お客さんが「このお店を人にすすめたいと思っているか」を測る指標。
- 質問例:
「このお店を友達や家族にすすめたいですか?(0〜10点)」 - 計算方法:
推奨者の割合 − 批判者の割合(%) - 活用例:
お客様の**ロイヤルティ(信頼・愛着)**を測る。
点数が高いほど、ファンが多いお店ということ。
4.ノーム値(Norm Value)
- 意味: あるデータの「業界や平均との比較基準」になる数値。
- 活用例:
自社の満足度アンケート結果が「4.2」だったとき、業界のノーム値が「3.8」なら良い成績といえる。
5.CVR(Conversion Rate|コンバージョン率)
- 意味: Webサイトなどで、どれだけの人が**最終的な行動(例:購入・申込)**をしたかを示す割合。
- 計算式:
コンバージョン数 ÷ アクセス数 × 100(%) - 活用例:
ECサイトで「100人中3人が買った」ならCVRは3%。
広告の効果やページの使いやすさを測るのに使われる。
NPS
19 商品やサービス、企業のロイヤルティを表すスコア。0~10の11段階で推奨度を評価してもらい、 0~6を批判者、7,8を中立者、9,10を推奨者とし、推奨者の割合から批判者の割合を引いた値を用い る。
語群 19 1.FSP 2.NPS 3.CVR 4.LBO 5.NRS
1.FSP(Frequent Shoppers Program|フリークエント・ショッパーズ・プログラム)
- 意味: お店によく来るお客様(リピーター)にポイントや特典を与えて再来店を促すプログラム。
- 例:
- ポイントカード制度
- アプリでスタンプを貯めて割引
- 目的: 顧客のロイヤルティ(愛着)を高めて、長期的な関係を築く。
- 小売での活用:
スーパーマーケットやドラッグストア、コンビニでよく導入されています。
2.NPS(Net Promoter Score|ネット・プロモーター・スコア)
- 意味: お客様が自社や商品を他人にどれくらいすすめたいと思っているかを数値で示す指標。
- 質問例:
「この店(ブランド)を友達や家族にすすめますか?(0〜10点)」 - 評価:
- 9〜10点:推奨者(ファン)
- 7〜8点:中立
- 0〜6点:批判者
- 計算式:
NPS = 推奨者の割合 − 批判者の割合(%) - 使い道:
顧客満足度やブランド力のモニタリングに使われます。
3.CVR(Conversion Rate|コンバージョン率)
- 意味: Webサイトや広告などで、どれだけの人が実際に購入や申込みなどのアクションをしたかを示す割合。
- 計算式:
CVR(%)= コンバージョン数 ÷ アクセス数 × 100 - 例:
- 100人が商品ページを見て、3人が購入 → CVR=3%
- 使い道:
- ECサイトの効果測定
- ランディングページの改善や広告の精度向上に役立つ
4.LBO(Leveraged Buyout|レバレッジド・バイアウト)
- 意味: 買収対象企業の資産や将来のキャッシュフローを担保にして、借金(負債)を使って企業を買収する方法。
- 特徴:
- 自己資金を少なく抑えて買収できる
- ハイリスク・ハイリターン
- 使い道:
- 投資ファンドなどが企業を買収するときに使う手法
- 小売業との関係:
海外ではLBOでスーパーや百貨店が買収されるケースもあります。
5.NRS(National Readership Survey|全国読者調査)※主に英国で使われる用語
- 意味: 雑誌や新聞などの読者層(性別・年齢・職業など)を調査したデータのこと。
- 用途:
- 広告主が「どのメディアに広告を出すか」を判断する材料
- 読者の購買行動やライフスタイルを把握するため
- 現在の名称: 英国では NRS は2018年以降、**PAMCo(Published Audience Measurement Company)**に統合されています。
※日本国内での「NRS」という略語が別の意味で使われている場合(例:マーケティング用語やPOS分析ツール名など)、補足可能ですので、もし他の意味を想定していたら教えてくださいね!
20 食料品販売店で売られている食材をその場で調理した料理が提供される。利用者がその料理を食べ て気にいれば、同じ食材を購入することができる。
グローサラント
語群 20 1.イートイン 2.フードコート 3.グローカランド 4.グローサラント 5.フードホール
1.イートイン(Eat-in)
- 意味: 飲食物を店内で食べるスタイルを指します。特にテイクアウトやデリバリーではなく、店舗内で食事を楽しむ形態。
- 活用例:
- カフェやファーストフード店などで提供される、食事を店内で楽しむためのスペース。
- 店内のテーブルや椅子を利用して、顧客がその場で食べられるようになっています。
- 例:
- スターバックスなどで、コーヒーを購入し、そのまま店内でくつろぎながら飲む。
2.フードコート(Food Court)
- 意味: 複数の飲食店が集まる共用スペースの中にある食事の提供エリア。主にショッピングモールや大型施設に設置されています。
- 特徴:
- セルフサービス形式で、各店舗から食べ物を購入し、共通のテーブルで食べる。
- 店舗ごとに異なる種類の料理が提供されることが多い。
- 活用例:
- ショッピングモールや空港などに多く見られる。
- 顧客は、さまざまな種類の料理を選ぶことができるため、家族や友人で異なる好みを持つ場合でも便利。
3.グローカランド(Glocaland)
- 意味: 「グローバル(Global)」と「ローカル(Local)」を組み合わせた造語で、地域に根ざしつつも世界的な視野を持つビジネスや商品展開を指します。
- 特徴:
- 世界的なブランドや商品を、地域ごとの文化やニーズに合わせてローカライズする考え方。
- グローバルとローカルの融合を目指す。
- 活用例:
- 海外の企業が日本市場に進出する際、日本特有の味やサービスを取り入れるケースがグローカランドの一例。
4.グローサラント(Grosserant)
- 意味: 食料品(グローサリー)とレストランを組み合わせた形態の店舗。食材を購入するだけでなく、その場で食事が楽しめる業態。
- 特徴:
- 食材販売とレストランが一体化しており、食材をそのまま購入して料理を楽しむことができる。
- 新鮮な食材を使った料理や、即席のメニューが提供される。
- 活用例:
- 大手スーパーやショッピングモールの中に、グローサラントが併設されている例が増えている。
- イオンなどが展開するフードマーケット内のレストランが一例。
5.フードホール(Food Hall)
- 意味: 多様な飲食店が集まる、屋内または屋外の広い飲食スペース。一般的に、店舗ごとに特色があり、食事を選びやすい形式。
- 特徴:
- フードコートに似ていますが、より洗練されたデザインや高級感のある場所であることが多い。
- 各店が提供する料理は、カジュアルなものからグルメまで様々なスタイルがあり、顧客は自由に選んで楽しむことができます。
- 活用例:
- 都市の中心地や高級ショッピングモール、空港に多く見られる。
- 高級感のある内装や多様な食文化を取り入れて、食事を楽しむだけでなく、社交の場としても利用されることが多い。
まとめ
SC経営士の試験に教科書はありません。過去問はすべての受験生が勉強していますので、落とさないようにしてください。

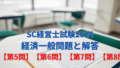
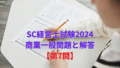
コメント