SC経営士試験2024SC管理問題と解答【第1~4問】
解答1から20まで、問題、解答はSC協会のHPから作成しています。問題の最後に用語の意味も記載しています。略語にはいくつかの意味がありますので、ご自分でも調べてください。
https://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html
一部AIによる解説も入れていますが、参考程度にご利用ください。
定期建物賃貸借契約
【第1問】〈配点 10点〉 (解答番号は 1 から 5 ) 定期建物賃貸借契約に関する次の文章を読み、文中の空欄に最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号 をマークしなさい。
定期建物賃貸借契約(以下、「定借契約」という)を有効に成立させるためには、契約書を書面で作成する ことが求められ、借地借家法第38条第1項には、 期間 の定めがある建物の賃貸借をする場合において は、 公正証書 による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がな いこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
なお、2021年9月1日に施行された「 デジタル 社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に よって、電子契約も可能となった。(第38条第2項)
定借契約を有効に成立させるための手続きとして、特に重要なのが、事前説明手続きで、契約締結に先立 ちテナントに対し十分に告知し注意喚起することで、テナントの保護を図るという目的で定められており、 説明する内容を記載した書面をテナントに交付すると同時に、 口頭 でも説明をする必要がある。 なお、テナントから事前に承諾を得れば、 電磁 的方法によって事前説明を行うことも可能となって いる。
語群( 1 〜 5 ) 1.金額 2.電磁 3.アナログ 4.期間 5.証明書 6.デジタル 7.面積 8.パソコン 9.ペーパーレス 10.電子 11.インターネット 12.公正証書 13.ブロードバンド 14.口答 15.口頭
金額(きんがく)
お金の合計や値段のこと。例えば、買い物や契約で支払うお金の量を指します。
電磁(でんじ)
電気と磁気に関する現象。例えば「電磁波」は、光や電波などを含む見えないエネルギーの波です。
アナログ
連続的に変化する情報を扱う方式。時計の針のように、なめらかに変わるもの。デジタルの反対。
期間(きかん)
ある始まりから終わりまでの時間の長さ。例:試験期間、契約期間。
証明書(しょうめいしょ)
あることが本当であると証明する文書。例:卒業証明書、住民票。
デジタル
情報を0と1の数字で表す方式。パソコンやスマホなどはすべてデジタル技術を使っています。
面積(めんせき)
土地や物の広さを表す数値。単位は平方メートル(㎡)など。
パソコン
パーソナルコンピューターの略。家庭や仕事で使うコンピューターのこと。
ペーパーレス
紙を使わずに、デジタルで文書などをやりとりすること。環境に優しい方法。
電子(でんし)
原子の中にある小さな粒で、電気の流れをつくる基本的な要素。電子メール、電子マネーなどの言葉にも使われます。
インターネット
世界中のコンピューターがつながって情報をやりとりできるネットワーク。Webサイトやメールなどに使われます。
公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人(法律の専門家)が作る、法的に強い効力を持つ文書。契約や遺言などで使われます。
ブロードバンド
大量のデータを高速で送ることができるインターネット回線。光回線などがこれにあたります。
口答(こうとう)
口で言うこと、言葉で伝えること。文書ではなく、話すことで情報を伝える形式。
口頭(こうとう)
話し言葉で伝えること。「口答」とほぼ同じ意味だが、やや形式的。例:口頭試問、口頭での説明。
SCに関する用語
【第2問】〈配点 10点〉 (解答番号は 6 から 10 ) 次の記述を読み、記述文と最も関連の深い語句をそれぞれの語群から選び、その番号をマークしなさい。
AM(Asset Management/アセットマネジメント)
6 投資家や資産所有者などから委託を受け、金融資産や不動産などの資産の総合的な運用・管理・ 運営を行う業務のこと。
語群 6 1.PM 2.AM 3.BM 4.FM 5.CM
【解説】
AM(Asset Management/アセットマネジメント)
投資家や資産の持ち主から委託を受けて、不動産や株式などの資産を総合的に管理・運用する業務のこと。例えば、不動産であれば、どこに投資するか、いつ売るかなどの判断を行います。
【他の用語の説明】
- PM(プロパティマネジメント)
建物の管理や入居者対応など、物件の運営管理をする仕事。不動産オーナーに代わって、家賃の集金、修繕対応などを行います。 - BM(ビルマネジメント)
建物設備の保守・点検・清掃などを担当する業務。施設が安全・快適に使えるように維持管理します。 - FM(ファシリティマネジメント)
会社などの施設全体(建物・設備・環境)の最適な管理を目指す仕事。経営の視点からコスト削減や効率向上を図ります。 - CM(コンストラクションマネジメント)
建設プロジェクトをマネジメントする業務。設計者や施工業者の調整、工事費の管理、スケジュール管理などを行います。
それぞれ、不動産や建設に関わるけれど、目的や関わるタイミングが違うのがポイントです。
O2O(Online to Offline)
7 オフラインの購買活動を促進するためにオンライン上で行われるマーケティング施策。一例では、 オンラインのECサイトを訪問したユーザーに実店舗で使用できるクーポンを配り、実店舗に来 店してもらう取り組み等。
語群 7 1.WEB 2.O2O 3.ICT 4.CRM 5.OMO
この設問の答えは、
2.O2O(Online to Offline) です。
【解説】
O2O(Online to Offline)
インターネット上の情報や広告などを使って、実際の店舗への来店や購入行動を促すマーケティング手法。
たとえば、ECサイトでクーポンを配って「このクーポンはお店で使えますよ」と誘導するような施策が代表例です。
【他の用語の説明】
- WEB(ウェブ)
インターネット上の情報の仕組みやサービスの総称。ホームページやSNS、ECサイトなどがこれに含まれます。 - ICT(Information and Communication Technology/情報通信技術)
コンピュータやネットワークを使って情報をやり取りしたり共有する技術。ITに「通信」の要素が加わった言葉。 - CRM(Customer Relationship Management/顧客関係管理)
顧客と長く良い関係を築くための仕組み。顧客データを使って、最適なサービスや情報を提供して満足度を上げます。 - OMO(Online Merges with Offline)
オンラインとオフラインを一体化して考えるマーケティング戦略。O2Oよりも進んだ概念で、たとえば実店舗での行動もデジタルで記録し、ネットと融合させて顧客体験を高めます。
内装監理
8 SCの各テナントの設計に対し、全体計画に基づく統制が必要な事項についての内装規制を定め、 設計・施工レベルの統一を図ること。また、建築施工者との円滑な調整、協議を実施しながら、全 体の工程管理を行う。
語群 8 1.内装監理 2.原状回復 3.デザイン規制 4.工事区分 5.設計指針
この設問の答えは、
1.内装監理(ないそうかんり) です。
【解説】
内装監理
ショッピングセンター(SC)などで、各テナントの内装について、全体のデザインやルールに沿うようにチェック・調整する業務です。
内装工事が全体のスケジュールに合っているか、ほかの業者とぶつからないか、建物全体の雰囲気に合っているかなどを監理します。
【他の用語の説明】
- 原状回復(げんじょうかいふく)
テナントが退去するときに、借りたときの状態に戻すこと。壁紙や床、設備などを元通りにする工事です。 - デザイン規制
施設全体の統一感を守るために、各テナントに対して色・形・サインなどのデザインに関するルールを設けること。 - 工事区分(こうじくぶん)
建築全体の中で、「どこを誰が工事するか」を分けて決めること。建物オーナー側とテナント側での分担を明確にします。 - 設計指針(せっけいししん)
設計の方向性やルールを定めたガイドライン。内装・設備・安全基準など、テナントの設計時に守るべき内容が書かれています。
9 顧客体験価値。体験価値とは、商品サービスの届け方を含むブランド総体として、顧客が実感でき る価値を指す。
CX(Customer Experience/カスタマーエクスペリエンス)
語群 9 1.CX 2.DX 3.CS 4.UX 5.ES
この設問の答えは、
1.CX(Customer Experience/カスタマーエクスペリエンス) です。
【解説】
CX(Customer Experience)
商品そのものだけでなく、「購入前の情報提供」「購入時の接客」「購入後のサポート」など、顧客がそのブランドやサービスを通して感じるすべての体験の価値のことを指します。
たとえば、同じ商品でも、接客が丁寧でワクワクする店舗で買えば、その体験ごと「いいブランド」と感じる、というのがCXの考え方です。
【他の用語の説明】
- DX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)
ITやデジタル技術を使って、ビジネスや働き方、社会全体をより良く変革していくこと。例:紙の申請書をスマホアプリに変えるなど。 - CS(Customer Satisfaction/カスタマーサティスファクション)
顧客満足度のこと。商品やサービスに対して、どれだけお客さんが満足したかを表します。 - UX(User Experience/ユーザーエクスペリエンス)
ユーザーが製品やサービスを使ったときの体験。CXと似ているが、UXは特にアプリやWebサイトなど「操作や使用感」に注目。 - ES(Employee Satisfaction/従業員満足度)
社員やスタッフが仕事や職場環境に満足しているかを表す指標。ESが高いと、CSも向上すると言われています。
アクワイアラー(Acquirer)
10 クレジットカードの国際ブランド(VisaやMasterCardなど)と加盟店を取り次ぐ会 社で、売上金の立て替えや加盟店の審査管理などを行う。
語群 10 1.CAT 2.イシュアー 3.アクワイアラー 4.日本クレジット協会 5.アライアンス
この設問の答えは、
3.アクワイアラー(Acquirer) です。
【解説】
アクワイアラー(Acquirer)
クレジットカードの加盟店(お店側)とカード会社(国際ブランドなど)の間を取り次ぐ会社のこと。
具体的には、以下のような役割を担っています:
- 加盟店の審査・契約
- カードでの支払いを処理
- 加盟店への売上金の立て替え払い
→つまり、「お店がカードで売り上げた分のお金を、いったんお店に払う役目」もしています。
【他の用語の説明】
- CAT(Credit Authorization Terminal)
クレジットカードの承認を行う端末機。レジ横にあるカードを通す機械のことです。 - イシュアー(Issuer)
クレジットカードを発行する会社のこと。例:三井住友カード、JCBなど。利用者に対して信用を与える立場。 - 日本クレジット協会
クレジット業界のルールづくりやトラブル防止、情報提供を行う業界団体。健全なカード利用のために活動しています。 - アライアンス(Alliance)
企業同士の提携・連携のこと。カード会社と航空会社が提携してポイントを共有する、などが例です。
SCのマネジメントに関する法律等
【第3問】〈配点 5点〉 (解答番号は 11 から 15 ) SCのマネジメントに関する法律等について、以下の記述のうち正しいものには1を、誤っているものには2 を、解答欄にマークしなさい。
労働者派遣法
11 派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とす る行為に協力してはならない。なお、派遣労働者等が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪 問もしくは履歴書の送付または派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣 労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能である。
1
この設問の答えは、
1(正しい) です。
【解説】
この設問は、「労働者派遣法」に関する内容です。
✔ ポイント:
派遣労働では、「誰を派遣するか」は派遣元(派遣会社)が決めることになっており、派遣先(働く場所の会社)が個人を特定して依頼するのは禁止されています(いわゆる「指名派遣」の禁止)。
ただし、「紹介予定派遣(=派遣後に正社員として雇うことを前提とした派遣)」の場合は、特定が認められています。
✔ 設問文のポイントを整理すると:
- 「紹介予定派遣でない」場合 → 派遣先が人を特定することは禁止。
- 派遣元も、それに協力してはいけない。
- しかし、派遣労働者本人が自分の意思で履歴書を送る・事業所訪問することは、違法ではない(特定目的の協力にはあたらない)。
➡ このすべてが労働者派遣法の規定と一致しています。
偽装請負、労働者派遣
12 労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されないためには、請負事業主が労働者の配置等の決定 を自ら行ってはならない。一方で、マネキンを含め、販売、サービスまたは保安等、「仕事を完成さ せ目的物を引き渡す」形態ではない請負業務では、請負業務を実施する日時、場所、標準的な必要人 数等を指定して発注したり、労働者の人数や労働時間に比例する形で料金決定したりすることに合 理的な理由がある場合はこの限りではない。
2
この設問の答えは、
2(誤っている) です。
【解説】
この問題は、**「偽装請負」や「労働者派遣との違い」**に関する法律知識が問われています。
✔ ポイント整理:
✅【請負契約とは】
請負契約は、「成果物(モノやサービス)を完成させて納品する契約」です。
そのため、本来は:
- 請負会社が自ら労働者の配置や指揮命令を行う
- 発注者(クライアント)は現場の労働者に直接指示してはいけない
というのが原則です。
❌ 設問の誤り部分:
「請負事業主が労働者の配置等の決定を自ら行ってはならない。」
これは誤りです。
→ むしろ、請負事業主が労働者の配置を自ら決めることが、請負としての要件の一つです。
もし発注者側(=依頼する会社)が労働者の配置を細かく指示していたら、それは「請負」ではなく「労働者派遣」と見なされるリスクがあります(=違法な「偽装請負」になる)。
✅「合理的な理由がある場合はこの限りではない」という記述にも注意:
たとえ販売やマネキンなどのサービス系の仕事であっても、労働時間・人数に比例した契約で、なおかつ発注者側が細かく指示していたら、実態は「派遣」とみなされます。
つまり、「合理的な理由があるからOK」とはならない。
✅ 結論:
文中にある「請負事業主が労働者の配置を行ってはならない」という点が誤りなので、
**答えは「2(誤っている)」**です。
労働関係調整法
13 労働関係調整法とは、労働関係の公正な調整をはかり、労働争議を予防または解決することを目的 とした法律。1946年(昭和21年)制定。労働争議についてその自主的解決を原則として、労働委員会 による調整方法として斡旋・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め、また争議行為の禁止・制限などを 規定する。
1
この設問の答えは、
1(正しい) です。
【解説】
労働関係調整法は、1946年(昭和21年)に制定された日本の法律で、労働関係の公正な調整を目指しています。主な目的は、労働争議を予防・解決することです。具体的には、労働争議(例えば、ストライキや労働者と経営者の対立)を解決するために、自主的な解決を原則としつつ、以下の方法を定めています。
✔ 主な内容:
- 労働委員会による調整方法:
- 斡旋:争議当事者に対して解決のための提案を行うこと。
- 調停:争議当事者間の交渉を助けて、合意を得るように働きかけること。
- 仲裁:第三者が問題解決のために決定を下すこと。
- 緊急調整:緊急の労働争議に対して、迅速に調整を行う方法。
- 争議行為の禁止・制限:
労働組合による過度な争議行為を防ぐための規制も設けられています。
公益通報
14 公益通報とは、企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働 者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれる)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的 でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいう。
1
この設問の答えは、
1(正しい) です。
【解説】
公益通報とは、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者、公務員など)や退職者、役員が、企業や事業者による違法行為や不正行為について、不正な目的でなく通報する行為を指します。通報の内容は、組織内の通報窓口や権限を持つ行政機関、または報道機関に対して行われます。
✔ 公益通報のポイント:
- 違法行為や不正行為に関する通報が対象。
- 通報者は、現役の労働者や退職者、役員など。
- 目的は不正の発覚と社会的な正義の実現であり、通報自体が違法でないこと。
- 通報窓口や行政機関、報道機関への通報が行われる。
このような制度は、内部告発とも呼ばれ、企業内部での不正を外部に報告することを通じて、企業の透明性や社会的責任を高めることを目的としています。
特定継続的役務提供
15 特定継続的役務提供とは「一定期間にわたって継続して提供されるサービス」のなかでも割賦販売 法のなかで規定されている3つの基準(業種・期間・金額)を満たすものを指す。業種ごとに期間と 金額が定められており、全てを満たすものが「特定継続的役務提供」に該当する。
2
この設問の答えは、
2(誤っている) です。
【解説】
特定継続的役務提供は、割賦販売法において規定されている概念で、一定の基準を満たす「継続的に提供されるサービス」のことを指します。このサービスが「特定継続的役務提供」に該当するためには、以下の3つの基準を満たす必要があります。
✔ 特定継続的役務提供の基準:
- 業種:特定の業種に限られます。例えば、通信、教育、医療などのサービスが該当する場合があります。
- 期間:サービスが一定期間(通常は2年以上)継続して提供されること。
- 金額:契約金額が一定額を超える(例:1年あたり5万円以上)場合。
❌ 誤り部分:
設問の記述に誤りがあります。
「業種ごとに期間と金額が定められている」という部分は、実際には業種ごとに基準が設けられていますが、業種ごとに個別に期間や金額が定められるわけではありません。
つまり、業種に関わらず、全体として**一定の期間(2年以上)と金額(年額5万円以上)**を満たす場合に該当します。
店舗の収益構造
【第4問】〈配点 10点〉 (解答番号は 16 から 20 ) 店舗の収益構造に関する次の文章を読み、文中の空欄に最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号をマ ークしなさい。
店舗の収益構造は、業種・業態によって大きく異なり、特に 物販 については、業態によって客単価 や1点単価、買上率、人件費率も変わってくる。
一般的には、スーパーマーケットやコンビニエンスストアのような客単価が低い業態ほど 来館頻度 は高く、 人件費率は低くなる傾向にある。逆に客単価の高いブランドショップでは、 来館頻度 は低いものの、接客 などが必要となるため人件費率は高くなる傾向にある。
店舗がSC等への出店を検討する際には、マーケットや 競合 状況、施設のポテンシャルを踏まえ想 定売上を試算し、業種業態によって異なる利益率から粗利を算出する。人件費や賃料などの ランニング コス トに投資回収コストを踏まえ、契約期間内で利益が残るかをシミュレーションし出店を判断する。特に飲食 では、設備投資等で出店コストがかかるため契約期間も長期になる傾向にあり、業態によって売上高に占め る粗利益の割合(粗利率または売上総利益率)は異なる。粗利益率は、食品スーパーで約 25
%、衣 料品チェーンで40~50%であることが多く、こうした収益構造の差がSCに出店した際の支払い可能な賃料 にもつながってくる。
語群( 16 〜 20 ) 1.来館頻度 2.1点単価 3.ランニング 4.競合 5.通販 6.減価償却 7.5 8.15 9.25 10.商圏 11.交通 12.キャペックス 13.サービス 14.イニシャル 15.物販
来館頻度
店舗や商業施設において、顧客がどれくらいの頻度で訪れるかを示す指標です。来館頻度が高ければ、売上の安定性やリピーターの多さを示すことができます。
1点単価
顧客が1回の購入で支払う金額を指します。小売業やサービス業では、1点単価を高めることが収益向上に繋がることがあります。
ランニング
通常、日々の運営や経費に関する用語です。ランニングコスト(運営コスト)やランニング経費(定期的に発生する費用)など、事業を続けるために必要な経費を指します。
競合
同じ市場で類似の商品やサービスを提供している企業や店舗のことを指します。競合企業との違いを出すことは、店舗の収益性向上において重要です。
通販
インターネットやカタログを通じて商品を販売する商業形態です。近年では、オンラインショッピングが非常に普及しており、実店舗の競合にもなっています。
減価償却
資産(主に設備や建物)の取得価額を、その使用可能期間にわたって経費として計上する会計処理方法です。設備投資に対して、徐々に費用化していく方法です。
5
特定の用語を意味するものではなく、通常は数値として使われます。文脈によって、例えば売上目標や利益率などを示す場合があります。
15
これも特定の用語を意味するものではなく、数値を指します。例えば、割合や売上の目標達成率などの数値に使われることがあります。
25
同様に、数値として使用される可能性があります。文脈によって、成長率や利益率などを示す場合があります。
商圏
特定の店舗がサービスを提供する地域の範囲を指します。商圏内の顧客層や人口動態などが、店舗の収益に大きな影響を与えます。
交通
交通量や交通の便の良さは、店舗の立地条件として重要な要素です。交通の便が良い場所に店舗を構えることは、集客力を高めるために有効です。
キャペックス
**Capital Expenditure(資本的支出)**の略で、設備投資や建物の購入など、長期的に使用するための支出を指します。通常、初期投資に関連する支出として使われます。
サービス
顧客に提供される非物質的な商品や支援を指します。サービス業では、サービスの質や顧客対応が収益に大きな影響を与えます。
イニシャル
**Initial(初期の)**の略で、初期費用や初期投資を指すことが多いです。店舗の立ち上げ時や新規事業にかかる初期投資などが含まれます。
物販
商品を販売する業態を指します。物販業では、商品の販売が収益の主要な柱となります。
まとめ
SC経営士の試験に教科書はありません。過去問はすべての受験生が勉強していますので、落とさないようにしてください。

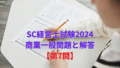

コメント