SC経営士試験2024商業一般問題と解答【第4問】【第5問】【第6問】
解答21から40まで、問題、解答はSC協会のHPから作成しています。問題の最後に用語の意味も記載しています。略語にはいくつかの意味がありますので、ご自分でも調べてください。
https://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html
一部AIによる解説も入れていますが、参考程度にご利用ください。
小売業のデジタルトランスフォーメーション
【第4問】〈配点 10点〉 (解答番号は 21 から 25 ) 小売業のデジタルトランスフォーメーションに関する次の文章を読み、文中の空欄に最も適切な語句を下記の それぞれの語群から選び、その番号をマークしなさい。
生活者の購買行動の多様化、人手不足の深刻化を受けて、デジタルトランスフォーメーション(以下DX) への取り組みは、小売業においても必要不可欠である。
決済におけるキャッシュレス化も、DXに欠かせない取り組みといえる。日本のキャッシュレス決済比率は、 世界各国と比べて低い水準となっている。そこで日本の「キャッシュレス決済比率」を2025年6月までに 40% 程度、将来的には世界最高水準の 22 を目指す「キャッシュレス・ビジョン」が2018年に公 表され、キャッシュレス決済の普及・拡大がすすめられてきた。
新型コロナウイルス感染症の拡がりで消費に関するオンライン化へのシフトも顕著となるなかで、2018年に 24.1%であったキャッシュレス決済比率は、2023年には39.3%まで高まり、目標に向けて順調に比率を伸ばし ている。キャッシュレス決済額について手段別の比率をみると、2023年は 23 が最も多く、 24 が これに続いている。
キャッシュレスを取り巻く環境も変化してきている。特に決済におけるスマートフォン等のモバイル端末の 利用やAI技術等の発展に伴う画像認識・データ分析技術などの新たな技術の登場は、キャッシュレスの提供 価値を拡大しうる変化といえる。たとえば顔認証による 25 決済、レジを通らず購入できる無人店舗な ど、よりシームレスで決済行動を意識せずに消費を完結できるサービスが登場している。
語群
21 1.40% 2.45% 3.50% 4.55% 5.60%
22 1.70% 2.75% 3.80% 4.85% 5.90%
23 1.クレジットカード 2.デビットカード 3.電子マネー 4.コード決済 5.暗号資産
24 1.クレジットカード 2.デビットカード 3.電子マネー 4.コード決済 5.暗号資産
25 1.VR 2.ハンズフリー 3.ハンズオン 4.AR 5.JWO
1.VR(Virtual Reality|仮想現実)
- 意味: コンピュータによって作り出された仮想の世界や環境にユーザーが没入できる技術。
- 特徴:
- ヘッドセットや専用の機器を使用して、実際には存在しない環境や状況を体験することができる。
- ゲームや教育、医療、建築などの分野で活用されている。
- 活用例:
- ゲーム:ユーザーが仮想の世界に入り込んで遊ぶ。
- 小売業:仮想店舗を体験したり、製品の3Dシミュレーションを行うために利用されることがあります。
2.ハンズフリー(Hands-free)
- 意味: 手を使わずに操作できる技術やデバイス。
- 特徴:
- 主に音声認識やジェスチャーで操作することができる。
- 通話や機器の操作を、手を使わずに行うことが可能。
- 活用例:
- Bluetoothイヤホンや**音声アシスタント(例:SiriやGoogle Assistant)**などで通話やメッセージの送受信を行う。
- 車のハンズフリー通話機能など、安全に運転しながら使える機器。
3.ハンズオン(Hands-on)
- 意味: 実際に手を使って操作する、または体験的な学習や活動を指す。
- 特徴:
- 理論や座学で学ぶのではなく、実際に自分の手で作業や操作を行うことが重要。
- 実践的な学習方法や体験型イベントでよく使われる。
- 活用例:
- 技術者のトレーニング:プログラミングや機械の操作を実際に行う。
- 製品展示:消費者が実際に商品を触って体験できるイベントや店舗。
4.AR(Augmented Reality|拡張現実)
- 意味: 現実の世界に、デジタル情報やオブジェクトを重ねて表示する技術。
- 特徴:
- スマートフォンや専用デバイスを通じて、現実の環境に仮想の情報を重ねて表示することができる。
- VRと異なり、現実の世界をそのまま見ることができるため、現実世界とデジタルの融合が可能。
- 活用例:
- 小売業:商品の情報やレビューを現実の商品の上に表示する、試着や色変更を仮想で体験する。
- 観光業:観光地で、スマホを通して歴史的な情報や遺跡の仮想復元を表示する。
5.JWO(Japan Warehouse Operation|日本倉庫運営)
- 意味: 日本国内での倉庫管理や運営に関する活動を指します。特に物流業界で使われることが多い用語。
- 特徴:
- 商品の保管、出荷、在庫管理などを含む、倉庫業務全般をカバー。
- 日本国内の効率的な物流システムや倉庫運営方法を指している場合が多い。
- 活用例:
- ECサイトなどで、商品の発送を管理するために効率的な倉庫運営やフルフィルメントを行う企業が増加している。
売場づくり
【第5問】〈配点 20点〉 (解答番号は 26 から 35 ) 次の文章は、売場づくりに関する文章である。正しいものには1を、誤っているものには2を、解答欄にマー クしなさい。
クロスマーチャンダイジング
26 クロスマーチャンダイジングとは、消費者の利用状況を考慮して、複数の商品(カテゴリー)を組み 合わせて陳列・演出し、買い物客に計画的購買を促す手法である。
2
クロスマーチャンダイジングについて
- 誤り(2)
クロスマーチャンダイジングは、異なる商品カテゴリーを組み合わせて陳列し、顧客に関連商品を一緒に購入させる戦略です。例えば、飲み物とおつまみを一緒に陳列することで、買い物客に一度に両方を購入させる手法です。
しかし、文中で言及されている「消費者の利用状況を考慮して」とありますが、この考慮は重要な要素ではあるものの、「計画的購買を促す」部分がクロスマーチャンダイジングの主目的ではなく、実際には関連商品を一緒に売ることが主な目的です。計画的購買を促すという表現は少しずれているため、誤りです。
インストアマーチャンダイジング
27 インストアマーチャンダイジングとは、広告や新聞折り込みによる販売促進ではなく、店内で実施 される売り場管理である。管理内容はインストアプロモーションとスペースマネジメントに分かれ る。
1
インストアマーチャンダイジングについて
- 正しい(1)
インストアマーチャンダイジングは、店内で行われる売場作りや商品管理の手法を指します。広告や新聞折り込みといった外部販促ではなく、店舗内で商品をどのように配置するか、どんな演出をするかに焦点を当てています。管理内容がインストアプロモーション(販促活動)とスペースマネジメント(陳列方法)に分かれる点は正しいです。
サービス動線
28 店舗においては、顧客が移動する経路をサービス動線と呼び、売場設計、レイアウトのベースとな る。サービス動線は短くするのが原則である。
2
サービス動線について
- 誤り(2)
店舗におけるサービス動線は、顧客が店舗内を移動する際の経路を指します。この経路は顧客が自然に移動しやすくなるよう設計されるべきです。文中の「サービス動線は短くするのが原則である」という部分は誤りです。顧客の動線は短くするだけでなく、効率的に移動できるように、また目的の商品にスムーズにアクセスできるように設計されることが重要です。
集視ポイント
29 集視ポイントとは、顧客の目を引き付け、足を止めさせ、計画的な購買に結び付けるための売場内 でのポイントとなる部分である。
2
集視ポイントについて
- 誤り(2)
集視ポイントは顧客が視線を向ける可能性が高い場所、つまり「視線を集める」売場の特定の位置です。これをうまく使って、顧客を引きつけ、足を止めさせ、購買へと導くことが目的ですが、**「計画的な購買に結びつけるための部分」**という表現は不完全です。集視ポイントは目を引く場所ですが、その後の購買行動に必ずしも結びつくとは限りません。
POP広告
30 売場におけるPOP広告は、商品と顧客をコミュニケートし、客数を増加させる購買促進策である。 商品の特徴や価格を説明して、顧客の目を引き付け、お買い得感を演出して購買意欲を喚起する。
2
POP広告について
- 誤り(2)
POP広告(Point of Purchase)は、店舗内で顧客に購買意欲を引き出すための宣伝ツールです。しかし、文中の「お買い得感を演出して購買意欲を喚起する」部分に関して、「POP広告はただ商品の特徴や価格を説明するだけ」という内容はやや単調です。実際、POP広告はその商品を強調し、視覚的に顧客を引き寄せることが重要です。お買い得感も一つの方法ですが、それだけではないため、文が不正確です。
パワーアイテム
31 パワーアイテムとは、販売数量が多く、顧客の支持率の高い商品である。パワーアイテムをバラン スよく店内に配置することによって、回遊性が向上する。
1
パワーアイテムについて
- 正しい(1)
パワーアイテムとは、顧客に高い需要があり、販売数量が多い商品のことです。これらを店内にバランスよく配置することで、顧客の「回遊性」を向上させることができます。例えば、売れ筋商品を目立つ場所に配置し、顧客が他の商品も手に取りやすくするという戦略です。
フェイシング
32 フェイシングとは、陳列棚の最前列に、同一かつ複数の商品を横と縦に最適な数量を並べる配列手 法である。売れ筋のフェイス数は多く、売れ行きが鈍い商品のフェイス数は少なくと、在庫量に応 じた陳列状態にするのが原則である。
2
フェイシングについて
- 誤り(2)
フェイシングは、棚の最前列に同一の商品を並べる陳列方法です。しかし、文中の「売れ筋のフェイス数は多く、売れ行きが鈍い商品のフェイス数は少なく」という部分は誤りです。実際には、売れ筋商品は多く陳列しますが、売れ行きが鈍い商品の場合、フェイシングを減らすのではなく、棚の場所や陳列方法を調整することが求められます。
デジタルサイネージ
33 屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場所でディスプレイなどの電子的な表示機器を使っ て情報を発信するシステムが、デジタルサイネージである。広告や施設案内などの多種多様な情報発 信に活用できる。
1
デジタルサイネージについて
- 正しい(1)
デジタルサイネージは、店舗や公共空間で使用される電子的なディスプレイを指し、広告や情報提供に活用されます。これには、店内ディスプレイや屋外広告、交通機関の案内板などが含まれ、情報発信の手段として非常に多岐にわたる活用がされています。
ゴールデンゾーン
34 目線を動かすことなく視界に入る陳列の高さの範囲は、ゴールデンゾーンと呼ばれる。商品が女性 向けか男性向けかで、ゴールデンゾーンの高低を意識する必要がある。例えば、玩具や菓子のゴンド ラでは、子供の目線に合わせて低くなる。
1
ゴールデンゾーンについて
- 正しい(1)
ゴールデンゾーンは、顧客の目線の高さに合わせた陳列の最適な位置で、特に目を引きやすい場所です。例えば、子供向けの商品は低い位置に陳列することが推奨されるため、ゴールデンゾーンの高低を商品によって意識することが重要です。
パラペット
35 パラペットとは、もとはフランス語で、店舗の正面の外観すべて、または外装全体のことである。パ ラペットの整備は、商業施設のイメージアップのためにも重要である。
2
パラペットについて
- 誤り(2)
パラペットは、通常、建物の屋上の縁部分を指し、外装や建物のデザインに関わる要素です。しかし、店舗の正面の外観を指す言葉として使うのは誤りです。パラペットの整備が商業施設のイメージアップに関わることはありますが、店舗外観全体という表現は不正確です。
主な業態
【第6問】〈配点 5点〉 (解答番号は 36 から 40 ) 以下の文章は、主な業態に関する記述である。文中の空欄に最も適切な語句を下記のそれぞれの語群から選び、 その番号をマークしなさい。
ドラッグストア業界
ドラッグストア業界は、 36 の向上や集客力の増強を図るため、 37 の拡大強化に邁進してき た。 37 の取り扱い強化による 38 ショッピングの強化や、諸外国人のインバウンド需要の取り 込みなどで、安定した成長を遂げたといえる。
語群
36 1.店格 2.生産性 3.来店頻度 4.認知度 5.従業員満足度
37 1.家庭雑貨 2.衣料品 3.サービス 4.医薬品 5.飲食料品
38 1.ネット 2.カタログ 3.テレビ 4.ワンストップ 5.ライブコマース
コンビニエンスストア
コンビニエンスストアの商品政策は、限定された品揃えのなかで、POSシステムを駆使した 39 手 法を採用している。店舗数の増加による競争も厳しく、近年ではやや成長鈍化の傾向がみられる。そこで採用 された商品政策が、 40 の導入である。 40 の導入により、家庭の主婦や高齢者層の集客に効果 を上げている。
語群
39 1.生産管理 2.人事管理 3.店舗管理 4.品質管理 5.単品管理
40 1.惣菜 2.生鮮三品 3.弁当 4.加工食品 5.書籍
36
1.店格
- 意味: 店舗の格付けやランクを指します。これは、店舗が提供する商品の価格帯やサービスの質によって、消費者に与える印象を評価する基準となります。
- 例: 高級ブランドを扱う店舗は「高級店格」に位置付けられ、日常的な商品を提供する店舗は「一般店格」とされることがあります。
2.生産性
- 意味: 労働力や資源を使ってどれだけの成果を上げられるかを測る指標です。小売業においては、店舗の売上高を従業員数で割った「売上高/従業員数」が生産性を示します。
- 例: 高い生産性を維持することは、利益を最大化するために重要です。
3.来店頻度
- 意味: 顧客が店舗に訪れる頻度を指します。来店頻度が高いほど、顧客のロイヤリティやリピート購入が期待でき、売上向上に寄与します。
- 例: 高頻度で来店する顧客層をターゲットにしたマーケティング戦略を取ることが有効です。
4.認知度
- 意味: あるブランドや店舗が消費者にどれだけ認知されているかを示す指標です。高い認知度は、広告やプロモーション活動の成果を反映します。
- 例: 新しい商品やサービスが市場に投入される際、まずは認知度を高めることが重要な戦略となります。
5.従業員満足度
- 意味: 従業員が自身の職場にどれだけ満足しているかを示す指標です。高い従業員満足度は、離職率の低下や業務の効率化、顧客サービス向上に繋がります。
- 例: 定期的なアンケートやフィードバックを通じて、従業員の満足度を評価し、改善策を講じる企業が多いです。
37
1.家庭雑貨
- 意味: 家庭用の日用品や雑貨を指します。これには、家庭で使用される小物や装飾品、日常的に使うアイテムが含まれます。
- 例: キッチン用品、掃除用具、バス用品など。
2.衣料品
- 意味: 服やアクセサリーなど、衣類に関連する商品です。ファッションや季節に応じた商品が多く、消費者のニーズが変動しやすいカテゴリです。
- 例: シャツ、ジーンズ、ドレス、ジャケットなど。
3.サービス
- 意味: 物理的な商品ではなく、提供される労働や手続きを含む事業を指します。小売業のサービスには、商品配送や修理、相談サービスなどが含まれます。
- 例: 銀行、保険、レストランの接客サービスなど。
4.医薬品
- 意味: 健康を維持または改善するために使用される薬品を指します。処方薬や市販薬を含みます。
- 例: 痛み止め、風邪薬、栄養補助食品など。
5.飲食料品
- 意味: 食品および飲料に関連する商品です。これには、日常的に消費される食べ物や飲み物が含まれます。
- 例: 野菜、肉、飲料水、アルコール飲料など。
38
1.ネット
- 意味: インターネット(ネットワーク)を指します。オンラインでの情報交換や商品購入などが行われる場所です。
- 例: ECサイトやSNSなど、オンライン活動に関連します。
2.カタログ
- 意味: 商品やサービスの一覧を載せた印刷物またはオンライン資料です。消費者に商品情報を提供するための手段です。
- 例: 新商品やセール情報を掲載した郵送カタログやオンラインカタログ。
3.テレビ
- 意味: 映像と音声を通じて情報を伝える放送メディア。テレビ広告は、商品のプロモーションやブランディングの手段として広く利用されます。
- 例: テレビCMを使った商品の認知度向上。
4.ワンストップ
- 意味: 一度の訪問で必要な全てのサービスや商品を提供することを指します。これにより、顧客は複数の場所を訪れる手間を省けます。
- 例: オンラインショッピングサイトで、商品の購入から配送まで一貫して行えるサービス。
5.ライブコマース
- 意味: リアルタイムで配信されるライブ動画を通じて、商品を紹介・販売する手法。視聴者が即時に商品を購入できる形式が特徴です。
- 例: InstagramやYouTubeのライブ配信で行われる商品販売。
39
1.生産管理
- 意味: 生産過程を効率的に管理するための活動です。これには、工場のライン管理や、原材料の調達、在庫管理などが含まれます。
- 例: 生産スケジュールを調整し、製造コストを最適化する活動。
2.人事管理
- 意味: 社員の採用、教育、評価、労務管理など、組織内の人材を管理することを指します。
- 例: 新人社員の研修や、給与の支払い管理など。
3.店舗管理
- 意味: 店舗運営に関する管理全般を指します。これには、商品陳列、スタッフの配置、売上管理などが含まれます。
- 例: 営業時間の管理や、販売促進活動の企画など。
4.品質管理
- 意味: 製品やサービスの品質を一定の基準に保つための活動です。製品の欠陥を防ぎ、顧客の満足度を確保します。
- 例: 定期的な品質チェックや、製造過程での品質監視。
5.単品管理
- 意味: 個別の商品の在庫や販売状況を管理する方法です。特定の商品がどれだけ売れたかを追跡し、必要な在庫を確保するための手法です。
- 例: 一つの商品ごとに、売れ行きのデータを収集して在庫を調整する。
40
1.惣菜
- 意味: 調理済みの食品で、家庭で調理せずにそのまま食べることができるものです。弁当などにも利用されます。
- 例: 揚げ物、煮物、サラダなど。
2.生鮮三品
- 意味: 生鮮食品の中で特に重要とされる3つのカテゴリー。野菜、魚、肉が一般的に生鮮三品として挙げられます。
- 例: 新鮮な野菜や魚、肉を販売するコーナー。
3.弁当
- 意味: 食事を一つの容器に詰めた食品。外出先や忙しい人々に人気です。
- 例: コンビニで販売されているおにぎり弁当や幕の内弁当。
4.加工食品
- 意味: 原材料を加工し、保存や調理をしやすくした食品。缶詰や冷凍食品などが含まれます。
- 例: インスタントラーメンや冷凍ピザ。
5.書籍
- 意味: 印刷された本や雑誌を指します。販売されることが多い商品で、知識や娯楽を提供します。
- 例: 小説や参考書。
これらの用語は、小売業や商品管理、サービス提供に関連する基本的な概念です。
まとめ
SC経営士の試験に教科書はありません。過去問はすべての受験生が勉強していますので、落とさないようにしてください。簿記の知識があれば簡単に解答できるレベルの問題です。過去問に慣れておきましょう。


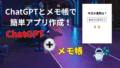
コメント