SC経営士試験2024経営戦略問題と解答【第14問】【第15問】
解答101から120まで、問題、解答はSC協会のHPから作成しています。問題の最後に用語の意味も記載しています。略語にはいくつかの意味がありますので、ご自分でも調べてください。
https://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html
一部AIによる解説も入れていますが、参考程度にご利用ください。
ROIC
【第14問】〈配点 10 点〉 (解答番号は 101 から 110 ) 次の文章は、「ROIC」に関する記述である。空欄に最も適切な語句を下記の語群から選び、解答欄にその番 号をマークしなさい。
ROIC
101 ROICとは 101 利益率のことで、企業もしくは事業の「稼ぐ力」を評価する指標であ る。
10.投下資本
102 ROICは、企業が調達した資本を事業に投下し、どれだけ効率よくNOPAT( 102 利 益)を生み出すことができているのかを測定する。
2.税引後営業
103 ROICの分母には、資金調達サイドに着目して「 103 と株主資本の合計額」とする方 法がある。
12.有利子負債
104 また、資金運用サイドに着目して「運転資本と 104 の合計額」を分母とする方法もある。
8.固定資産
WACC
105 WACCとは、「 105 資本コスト」のことで、企業が金融機関等や株主から資金を調達す るために必要となるコストを算出する方法のことである。
5.加重平均
ROICとWACC
106 健全な経営状態を保つためには、ROICがWACCを 106 いる必要がある。資金調達 コストよりも、事業等から生み出される運用利回りが大きくなる必要があるからである。
3.上回って
ROE
107 ROICと関連性の高い指標としての「ROE」は、「 107 利益率」である。
14.自己資本
108 ROEは、株主の投資がどれだけ 108 に還元されるかが把握しやすいため、「投資家目線 での指標」として用いられる。
6.配当金
ROA
109 ROAは、「 109 利益率」のことで、企業が保有している全ての資産がどれだけ利益につ ながっているかを示すための指標である。
4.総資産
ROIC、ROE、ROA
110 ROIC、ROE、ROAは、いずれも財務指標として企業の 110 や効率性を評価する ために使用される。
11.収益性
語群( 101 〜 110 ) 1.経常利益 2.税引後営業 3.上回って 4.総資産 5.加重平均 6.配当金 7.下回って 8.固定資産 9.純資産 10.投下資本 11.収益性 12.有利子負債 13.成長性 14.自己資本 15.流動資産
1.経常利益(けいじょうりえき)
意味: 本業の利益に加えて、財務活動(受取利息や支払利息など)を含めた企業の通常の活動による利益。
ポイント: 企業の安定的な儲けの力を示す指標です。
2.税引後営業利益(ぜいびきごえいぎょうりえき)
意味: 営業利益から税金を差し引いた後の利益。
ポイント: 営業活動だけでどれだけ純粋に儲けたかを表します。
3.上回って(うわまわって)
意味: 数値や基準がある値を超えること。
例: 売上が予想を上回った → 実際の売上が予想より高かった。
4.総資産(そうしさん)
意味: 企業が持つすべての資産の合計。
内訳: 流動資産+固定資産。会社の「持ち物」の全体像です。
5.加重平均(かじゅうへいきん)
意味: 要素ごとに重み(比重)をかけて計算した平均。
例: 株式の平均購入価格などに使われる手法。
6.配当金(はいとうきん)
意味: 会社が利益の一部を株主に分配するお金。
ポイント: 投資家への利益還元方法のひとつ。
7.下回って(したまわって)
意味: 数値や基準がある値よりも低いこと。
例: 利益が前年を下回った → 去年より少なかった。
8.固定資産(こていしさん)
意味: 長期間(1年以上)にわたって使う資産。
例: 建物、土地、設備、機械など。
9.純資産(じゅんしさん)
意味: 総資産から負債を引いた残り。会社の本当の「持ち分」。
式: 純資産=総資産-負債。
10.投下資本(とうかしほん)
意味: 事業活動のために企業が投入しているお金。
例: 設備や人件費に使うために投じた資本。
11.収益性(しゅうえきせい)
意味: 企業が効率よく利益を生み出せるかどうかを表す力。
例: 売上高利益率などで判断される。
12.有利子負債(ゆうりしふさい)
意味: 利息を払う義務がある借金(借入金や社債など)。
ポイント: 返済義務があり、企業の財務負担となる。
13.成長性(せいちょうせい)
意味: 企業が将来的にどれだけ伸びる可能性があるかを示す。
例: 売上や利益が毎年増えている企業は成長性が高い。
14.自己資本(じこしほん)
意味: 会社自身が持っている資本。株主資本とも呼ばれる。
式: 自己資本=純資産の一部。
15.流動資産(りゅうどうしさん)
意味: 短期間(1年以内)で現金化できる資産。
例: 現金、預金、売掛金、在庫など。
職場環境
【第15問】〈配点 10 点〉 (解答番号は 111 から 120 ) 次の文章は、「職場環境」に関する記述である。正しいものには1を、誤っているものには2を、解答欄にマー クしなさい。 (注)1.「改正育児・介護休業法」とは、2025 年 4 月 1 日に施行される「育児休業、介護休業等育児又 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正法の略称。 2.各種ハラスメントは、略称で記載している。
パワハラ防止措置
111 「パワハラ防止措置」は、男女雇用機会均等法に基づいて中小企業の事業主にも義務化されてい る。
2
セクハラ
112 職場における「セクハラ」は、男女雇用機会均等法により、事業主に防止措置を講じることが義務 付けられている。
1
マタハラ
113 職場における「マタハラ」は、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法で、事業主に防止措置 を講じることが義務付けられている。
1
カスハラ
114 「カスハラ」とは、顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求や迷惑行為のことであり、改 正労働施策総合推進法で明確に定義されている。
2
フリーランス保護法
115 フリーランス保護法は、下請法とは異なり、取引におけるフリーランスの保護だけでなく、ハラ スメント防止措置の義務付けや募集の適正化などといったフリーランスの就業環境整備も内容と している。 【「改正育児・介護休業法」について】
1
女性の育休取得率の公表義務
116 女性の育休取得率の公表義務の対象を、従業員数 1,000 人超の企業から 300 人超に拡大し、取得 率の目標値も 300 人超の企業は公表が義務となる。
2
育児休業
117 3 歳未満の子を養育する労働者が育児休業をしていない場合、テレワークで働ける環境を整える ことが事業主の努力義務になる。
1
企業の義務
118 3 歳から小学校就学前までの子どもを持つ親も柔軟に働けるようにするために、テレワークや短 時間勤務制度、フレックス制度などから 2 つ以上を選択して制度として設けることが企業の義務 になる。
1
残業
119 現在、残業は子が 3 歳になるまで免除されているが、これを小学校就学前までに延長する。
1
男性育休取得率
120 2025 年の男性育休取得率の政府目標は、40%に引き上げられた。
2
111:「パワハラ防止措置」は、男女雇用機会均等法に基づいて中小企業の事業主にも義務化されている。 → 2(誤り)
👉 解説:
パワハラ防止措置は「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」に基づくもので、男女雇用機会均等法ではありません。 なお、中小企業にも2022年4月から義務化されています。
112:「セクハラ」は、男女雇用機会均等法により、事業主に防止措置を講じることが義務付けられている。 → 1(正しい)
👉 解説:
セクハラ防止措置は、男女雇用機会均等法第11条で事業主に義務付けられています。相談窓口の設置や再発防止策などが求められます。
113:「マタハラ」は、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法で、事業主に防止措置を講じることが義務付けられている。 → 1(正しい)
👉 解説:
妊娠・出産に関する嫌がらせ(マタハラ)は、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の両方で防止措置が義務付けられています。
114:「カスハラ」は、顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求や迷惑行為のことであり、改正労働施策総合推進法で明確に定義されている。 → 2(誤り)
👉 解説:
「カスハラ(カスタマーハラスメント)」という言葉は広まっていますが、労働施策総合推進法で明確な定義はされていません。 ただし、厚労省が企業に対して対応策のガイドラインを示しています。
115:フリーランス保護法は、下請法とは異なり、取引におけるフリーランスの保護だけでなく、ハラスメント防止措置の義務付けや募集の適正化などといったフリーランスの就業環境整備も内容としている。 → 1(正しい)
👉 解説:
**2023年成立の「フリーランス保護新法」**では、取引上の保護だけでなく、ハラスメント対策や募集時の明確な条件提示など、働く環境全般を整える内容が含まれています。
116:女性の育休取得率の公表義務の対象を、従業員数1,000人超の企業から300人超に拡大し、取得率の目標値も300人超の企業は公表が義務となる。 → 2(誤り)
👉 解説:
現在、育休取得率の公表義務は1,000人超の企業のみが対象です。300人超の企業に対しては、努力義務の範囲となっています(義務ではない)。
117:3歳未満の子を養育する労働者が育児休業をしていない場合、テレワークで働ける環境を整えることが事業主の努力義務になる。 → 1(正しい)
👉 解説:
**改正育児・介護休業法(2023年)**により、育休を取らない労働者に対しても、テレワークなど柔軟な働き方の環境整備は事業主の努力義務になっています。
118:3歳から小学校就学前までの子どもを持つ親も柔軟に働けるようにするために、テレワークや短時間勤務制度、フレックス制度などから2つ以上を選択して制度として設けることが企業の義務になる。 → 1(正しい)
👉 解説:
2024年施行の改正育児・介護休業法により、柔軟な働き方支援として、選択肢を設けることが企業に義務付けられています。
119:現在、残業は子が3歳になるまで免除されているが、これを小学校就学前までに延長する。 → 1(正しい)
👉 解説:
2025年4月施行予定の改正により、時間外労働の制限期間が小学校就学前まで延長される予定です。
120:2025年の男性育休取得率の政府目標は、40%に引き上げられた。 → 2(誤り)
👉 解説:
政府目標は「50%」です(2025年)。現在の達成率は20%台で、目標に向けて制度拡充が進められています。
まとめ
SC経営士の試験に教科書はありません。過去問はすべての受験生が勉強していますので、落とさないようにしてください。



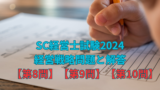
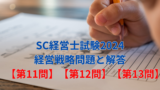
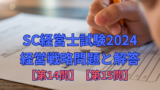
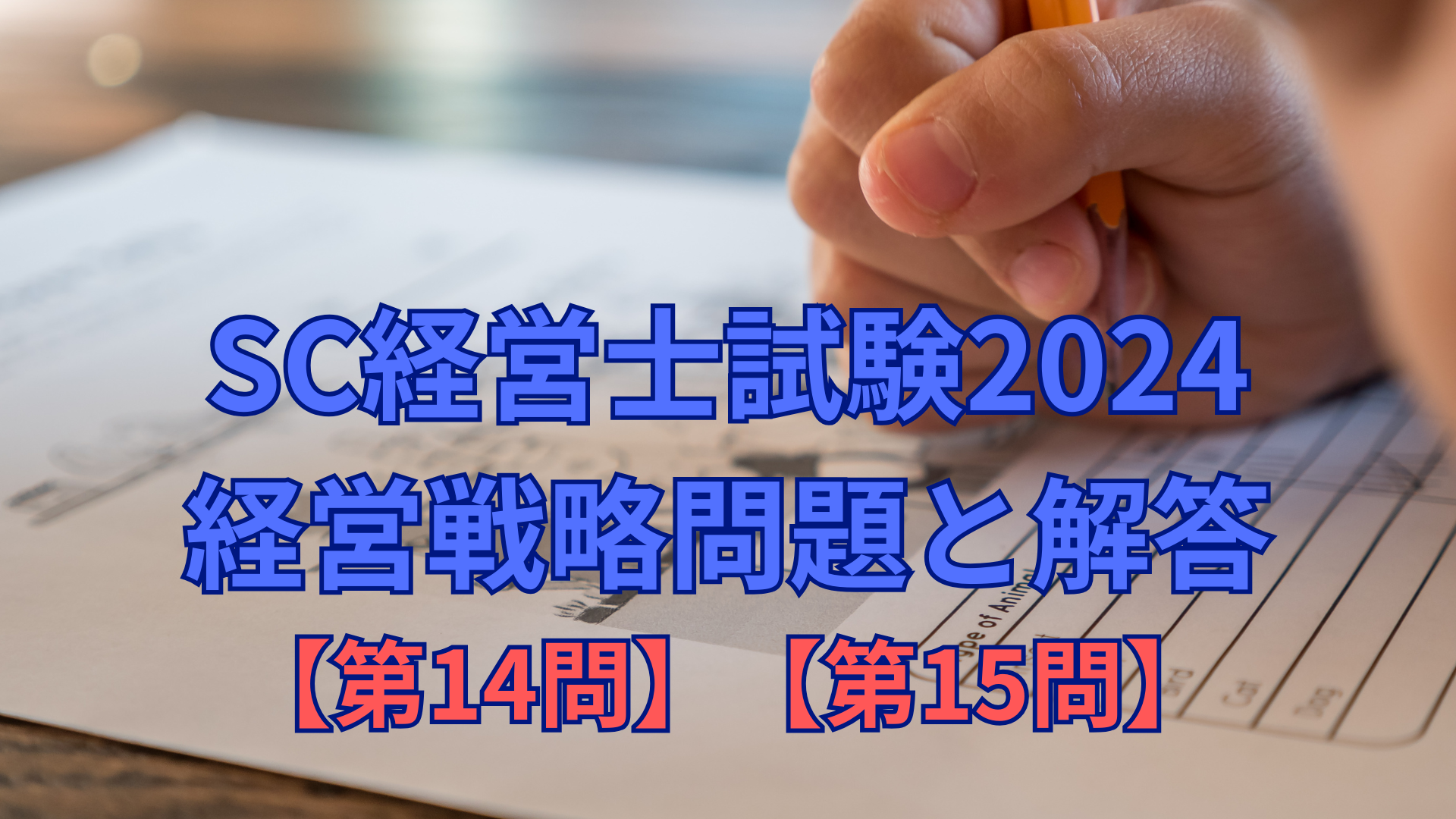


コメント