SC経営士試験2024経営戦略問題と解答【第8問】【第9問】【第10問】
SC経営士試験2024経営戦略問題と解答【第8問】【第9問】【第10問】解答61から80まで、問題、解答はSC協会のHPから作成しています。問題の最後に用語の意味も記載しています。略語にはいくつかの意味がありますので、ご自分でも調べてください。
https://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html
一部AIによる解説も入れていますが、参考程度にご利用ください。
生産性と付加価値
【第8問】〈配点 10 点〉 (解答番号は 61 から 65 ) 次の文章は、「生産性と付加価値」に関する記述である。空欄に最も適切な語句を下記の語群から選び、解答欄 にその番号をマークしなさい。
生産性とは
61 生産性とは、製品・ 61 を生産するために、投入する労働力や機械設備、原材料などがどれ だけ効率的に使用されたかを示すもので、算式で表すと 生産性=生産量(Output)÷投入量(Input)となる。
語群 61 1.技術 2.半導体 3.サービス 4.食料 5.素材
文を完成させるための語句は「3.サービス」です。
以下は各用語の説明です:
- 技術(Technology)
生産活動や業務運営を効率化するための科学的な方法、工具、技術体系を指します。技術は製造業やサービス業において重要な役割を果たし、生産性の向上に貢献します。 - 半導体(Semiconductor)
電気を通す特性を持つ材料で、主に電子機器に使用される部品。パソコンやスマートフォン、テレビなど、現代のテクノロジーに欠かせない重要な要素です。 - サービス(Service)
物理的な製品ではなく、顧客のニーズに応じて提供される活動や便益。例えば、金融サービス、健康サービス、教育サービスなどが含まれます。 - 食料(Food)
人や動物が生きるために必要な栄養素を供給する物質。農業や加工業を通じて生産され、消費者に提供されます。 - 素材(Material)
製品を作るための基本的な原料や資源。例えば、金属、木材、プラスチックなどが素材にあたります。素材は製品製造のための出発点となります。
文全体の意味は、生産性がどれだけ効率的にリソースを使って製品やサービスを生み出しているかを示す指標であることを説明しています。
付加価値とは
62 付加価値とは、技術やノウハウ、独自の仕入ルートなどにより企業が原材料に新たに創出、付加し た独自の価値である。付加価値の創出は、企業や産業の 62 を高める上で重要な要素である。
語群 62 1.競争力 2.資金力 3.人的資源 4.購買力 5.情報力
文を完成させるための語句は「1.競争力」です。
以下は各用語の説明です:
- 競争力(Competitiveness)
企業や産業が市場で他の企業と競り合うための力。競争力は、製品やサービスの品質、価格、ブランド力、技術力などによって決まります。付加価値を創出することで、企業は競争力を高め、市場での優位性を獲得できます。 - 資金力(Financial Strength)
企業がどれだけの資金を保有しているか、または資金調達の能力。資金力は、事業の成長や投資、リスクへの対応に必要不可欠です。 - 人的資源(Human Resources)
企業が持つ労働力や従業員の総称。人的資源は、企業の成長や競争力を支える重要な要素です。適切な人材を確保し、育成することが企業の成功に繋がります。 - 購買力(Purchasing Power)
消費者や企業が商品やサービスを購入する能力。購買力が高ければ、企業は製品を販売しやすくなり、市場でのシェアを拡大することができます。 - 情報力(Information Power)
企業が持つ情報の量や質、その情報を活用する能力。情報力は、意思決定を支え、競争優位性を確立するために重要です。データの活用や分析が効果的であれば、企業は市場で有利に立つことができます。
文全体の意味は、企業が技術やノウハウを駆使して原材料に新たな価値を付加し、その結果として企業や産業の競争力が向上することを強調しています。
付加価値の算出
63 付加価値の算出には、2 つの方法があるが、「控除法」による算式は 付加価値額=売上高- 63 価額である。
語群 63 1.減価償却 2.材料 3.人件費 4.外注加工 5.外部購入
減価償却(Depreciation)
資産(主に設備や建物など)の価値が時間とともに減少することを計上する会計処理。企業は減価償却を通じて、資産の使用に伴うコストを経費として計上し、税務上の利益を減少させることができます。
材料(Materials)
製品を作るための基本的な原材料。製造業などでは、原材料費は生産過程において最も基本的で大きなコストの一つです。付加価値を計算する際、材料費を引くことで、企業がどれだけの付加価値を生み出したかを把握することができます。
人件費(Labor Cost)
従業員の給与や賃金、福利厚生など、企業が労働力に支払う費用。付加価値を生み出すための労働力コストとして重要な要素です。
外注加工(Outsourcing Processing)
自社で行うべき業務や作業を外部の企業に委託すること。外注費は、企業のコスト構造において重要な要素となり、付加価値計算時にも考慮される場合があります。
外部購入(External Purchases)
企業が自社で製造せず、外部から購入する製品や部品。これも付加価値算出時に考慮される要素であり、外部から購入した商品はそのまま売上高から差し引かれることがあります。
労働分配率
64 労働分配率は企業が生み出した付加価値に対する人件費の割合を表す指標であり、利益をどれだけ 従業員に 64 したかを測る指標である。
語群 64 1.縮減 2.還元 3.回復 4.節減 5.軽減
文を完成させるための語句は「2.還元」です。
以下は各用語の説明です:
- 縮減(Reduction)
減少や削減を意味します。特にコストや規模の縮小を指すことが多く、企業の経営効率を高めるために行われることがあります。 - 還元(Return)
投資や成果を返すことを意味します。この文脈では、企業が得た利益や付加価値を従業員に「還元する」ことを指し、人件費の支払いやボーナス、給与として従業員に還元される部分を測る指標です。 - 回復(Recovery)
失われた状態からの回復を意味します。経済や企業の状況が悪化した後に元の状態に戻すことを指します。 - 節減(Saving)
コストや経費を削減することを指します。企業の支出を減らし、効率的に資源を使うために行われることが多いです。 - 軽減(Mitigation)
影響やコストを軽くすることを意味します。リスクや負担を減らすために取る措置を指します。
文全体の意味は、労働分配率が企業が生み出した付加価値に対する人件費の割合を示し、どれだけ企業がその成果を従業員に還元したかを測る指標であることを示しています。
有形固定資産回転率
65 有形固定資産回転率は、企業が所有する有形固定資産を効果的に活用しているかどうかを示す指標 の一つである。同業種と比較して有形固定資産回転率が低い場合は、売上高を伸ばすか、有形固定資 産額を 65 かによって経営の軌道修正に役立てる。
語群 65 1.節税する 2.削除する 3.増やす 4.減らす 5.維持する
文を完成させるための語句は「4.減らす」です。
以下は各用語の説明です:
- 節税する(Tax saving)
税金を減らすための行為。企業が合法的に税負担を軽減するために取る措置です。税控除や減税措置を活用することなどが含まれます。 - 削除する(Delete)
何かを取り除く、削り取ることを指します。例えば、データや不要な項目を削除することを指しますが、この文脈には合いません。 - 増やす(Increase)
数量を増やすことを意味します。売上や資産、収益などを増加させることを指しますが、回転率が低い場合には、必ずしも増やすことが最適とは限りません。 - 減らす(Reduce)
数量を減少させることを意味します。この文脈では、有形固定資産額が過剰である場合、減らすことが適切な経営改善手段となることを示しています。過剰な資産を持っていると、効率が悪くなり、回転率が低下するため、適切に資産を減らすことが重要です。 - 維持する(Maintain)
現状を維持することを意味します。資産の維持や維持管理に関する活動ですが、効率的な資産運用を目指す場合、単に維持するだけでは足りません。
文全体の意味は、有形固定資産回転率が低い場合、企業は売上を伸ばすか、資産額を減らして経営効率を改善する必要があることを指摘しています。
事業継続マネジメント
【第9問】〈配点 10 点〉 (解答番号は 66 から 70 ) 次の文章は、「事業継続マネジメント」に関する記述である。空欄に最も適切な語句を下記の語群から選び、解 答欄にその番号をマークしなさい。
事業影響度分析(BIA)
66 事業影響度分析(BIA)とは、事業の中断による、業務上や財務上の影響を確認するプロセスのこ と。重要な事業・業務・プロセスおよびそれに関連する経営資源を特定し、事業継続に及ぼす経営等 への影響を時系列に分析を行う。例えば、①重要な事業の 66 、②ビジネスプロセスの分析、 ③事業継続に当たっての重要な要素(ボトルネック)の特定、④復旧優先順位の決定、⑤目標復旧時 間・目標復旧レベルの設定の手順を踏む。
7.洗い出し
事業継続計画(BCP)
67 事業継続計画(BCP)とは、大地震等の自然災害、 67 のまん延、テロ等の事件、大事故、 サプライチェーンの途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中 断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した 計画のことである。
10.感染症
事業継続マネジメント(BCM)
68 事業継続マネジメント(BCM)とは、BCP策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・ 資源の確保、対策の実施、取組を浸透させるための 68 の実施、点検、継続的な改善などを 行う平常時からのマネジメント活動のことである。経営レベルの戦略的活動として位置付けられる。
3.教育・訓練
リスク分析・評価
69 リスク分析・評価とは、 69 の原因となる発生事象(インシデント)を洗い出し、それらの 発生の可能性と影響度を評価することで優先的に対応すべき発生事象を特定し、当該発生事象によ り生じるリスクがもたらす被害等の分析・評価を実施することである。
14.事業中断
情報セキュリティガバナンス
70 情報セキュリティガバナンスとは、社会的責任にも配慮したコーポレートガバナンス(企業の意思 決定の仕組み)とそれを支えるメカニズムである 70 の仕組み(企業が業務を適正かつ効率 的に遂行するために構築・運用される社内体制およびプロセス)を、情報セキュリティの観点から企 業内に構築・運用することである。
2.内部統制
語群( 66 〜 70 ) 1.可視化 2.内部統制 3.教育・訓練 4.意見交換 5.アドバイス 6.風評 7.洗い出し 8.ストライキ 9.内部監督 10.感染症 11.稼ぎ方 12.事業継続 13.第三者管理 14.事業中断 15.洗い替え
可視化(Visualization)
複雑なデータや情報を視覚的に表現すること。グラフや図、チャートを使って理解しやすくするプロセスで、データ分析や意思決定に役立ちます。
意見交換(Exchange of opinions)
あるテーマについて、複数の人々が自分の考えや意見を出し合うこと。議論やディスカッションを通じて異なる視点や意見を交換することによって、より良い解決策を見つけるための重要なプロセスです。
アドバイス(Advice)
問題や課題に対して、他者から提供される助言や提案。経験や知識に基づいて、何かをする方法や方針を助けるために与えられる指導や助言です。
風評(Rumor/Heard opinion)
真実であるかどうか確証がないが、広まっている噂や評価。特に企業や商品、個人に関する根拠のない噂や社会的な評判を指します。風評が悪化することによって、信頼やイメージが損なわれることがあります。
ストライキ(Strike)
労働者が自分たちの労働条件を改善するために、仕事を停止して抗議する行為。労働争議の一形態で、労働者が労働条件の変更を求めて行う集団行動です。
内部監督(Internal supervision)
企業や組織内で、業務や活動が適切に行われているかどうかを監視する活動。企業の内部統制の一環として、法令遵守や業務改善、リスク管理を目的として行われます。
稼ぎ方事業(Revenue-generating business)
企業や個人が利益を得るために運営する事業。利益を上げるための戦略や手法を指し、商業活動の根幹にあたるものです。
継続(Continuation)
物事が途中で止まることなく、続けて行われること。企業活動や計画が途中で中断せずに進行することを指し、持続可能な運営を意味します。
第三者管理(Third-party management)
企業や組織の業務や資産を、外部の専門機関や第三者に委託して管理すること。例えば、外部のコンサルタントや管理会社が担当する形です。
洗い替え(Replacing/Refurbishing)
古くなったり劣化したものを新しいものに取り替えること。特に設備やシステム、施設などが劣化した場合に行う交換作業を指します。
マーケティング用語
【第10問】〈配点 10 点〉 (解答番号は 71 から 80 ) 次の文章は、「マーケティング用語」に関する記述である。空欄に最も適切な語句を下記の語群から選び、解答 欄にその番号をマークしなさい。
ペルソナ
71 71 とは、自社のサービスや商品を利用する典型的な顧客の人物像のこと。
語群 1.キャラクター 2.ペルソナ 3.個客
カスタマージャーニー
72 72 とは、顧客が商品やサービスを認知し、購入を決定するまでのプロセスのこと。
語群 1.顧客分析 2.デジタル分析 3.カスタマージャーニー
セグメント
73 73 とは、市場に存在する様々な属性を持った不特定多数の人々を、同じニーズや性質を持 つグループに分類すること。
語群 1.ドメイン 2.セグメント 3.ポジショニング
リスティング
74 74 とは、複数あるデータのなかから、特定の条件に基づいてデータを抽出すること。
語群 1.テキスト 2.リスティング 3.SEO
オムニチャネル
75 75 とは、実店舗やECサイト、SNSなどのあらゆる販売チャネルを活用して顧客と接点 を持ち、アプローチする販売戦略のこと。
語群 1.オムニチャネル 2.シームレス 3.One to One
キャラクター(Character)
商品やブランド、サービスのイメージを形成するために使用される、人物やキャラクター(マスコット)などの象徴的な存在。消費者に親しみを持たせたり、ブランド認知度を高めるために使われます。例えば、アニメキャラクターや企業のマスコットなどが例です。
個客(Individual customer)
「個客」とは、1人1人の顧客のことを指します。企業やマーケティングの観点では、顧客を個々に特定して理解し、それぞれに最適な商品やサービスを提供することが重視されています。顧客一人一人に焦点を当てた戦略が重要です。
顧客分析(Customer Analysis)
顧客分析は、顧客の特性やニーズ、行動パターンを把握し、マーケティング戦略を立てるためのデータ収集・分析のことです。ターゲット層の理解を深めるために行い、顧客満足度の向上やリピーターの獲得を目指します。
デジタル分析(Digital Analytics)
デジタル分析は、WebサイトやSNS、オンライン広告など、デジタルチャネルを通じた顧客の行動や反応を収集・分析することです。アクセス解析やコンバージョン率の分析などを行い、オンラインマーケティング活動の効果を測定し、最適化するために使用されます。
ドメイン(Domain)
ドメインは、オンラインで使用されるウェブサイトの「住所」や「範囲」を意味します。マーケティングにおいては、特定の市場やビジネス分野を指すこともあり、企業が活動している分野や領域を示す場合もあります。例えば、IT業界の「ドメイン」や「デジタルマーケティングのドメイン」などです。
ポジショニング(Positioning)
ポジショニングは、競合他社と比較して、自社のブランドや製品を市場でどのように位置づけるかを決定するプロセスです。消費者の心の中でどのような立ち位置を占めたいかを明確にすることが、マーケティング戦略の鍵となります。
テキスト(Text)
マーケティングにおけるテキストは、広告やコンテンツに使用される文章を指します。ウェブサイトやメールマーケティング、SNSなどで使われるテキストは、消費者に訴求するために非常に重要で、訴求力のある文言が求められます。
SEO(Search Engine Optimization)
SEOは、検索エンジン最適化の略で、Googleなどの検索エンジンで自社のウェブサイトを上位に表示させるための手法です。コンテンツの質、リンクの活用、キーワードの選定などを駆使して、自然検索からの集客を狙います。
シームレス(Seamless)
シームレスとは、異なるプロセスやプラットフォームが互いに繋がり、途切れなくスムーズに操作や体験が進むことを意味します。オンラインとオフラインが一体化した体験など、顧客にとってストレスなく一貫性のあるサービスが提供される状態を指します。
One to One(ワントゥーワン)
ワントゥーワンマーケティングは、顧客一人一人に対して個別のアプローチを行うマーケティング戦略です。データを活用して、個別のニーズに合わせた商品やサービスを提供し、個別対応の強化を図ります。ターゲット層の細分化とパーソナライズ化が特徴です。
5A(ファイブ・エー)
76 76 とは、マーケティング 4.0 における考え方で、購買におけるそれぞれのプロセスにそっ て顧客にアプローチし、顧客を理解しながらマーケティングを行うこと。
語群 1.5A 2.4P 3.5F
以下に、マーケティングにおける「5A」「4P」「5F」それぞれの用語をわかりやすく解説します。
1.5A(ファイブ・エー)
「顧客の購買行動のプロセス」を表すフレームワーク
フィリップ・コトラーが提唱したモデルで、デジタル時代の消費者行動を説明しています。
| 段階 | 意味 | 説明 |
| Aware(認知) | 商品・ブランドを知る | |
| Appeal(興味) | 興味や好感を持つ | |
| Ask(調査) | 情報を調べたり、人に聞いたりする | |
| Act(購買) | 実際に購入・利用する | |
| Advocate(推奨) | 他人に勧める(ファン化) |
✅ ポイント:現代では「情報収集(Ask)」が特に重要視され、SNSや口コミが消費者の意思決定に強く影響します。
2.4P(マーケティング・ミックス)
「企業視点」で商品・サービスを市場に提供する際の4つの要素
| 要素 | 日本語 | 内容の例 |
| Product | 製品 | 商品の機能・デザイン・品質など |
| Price | 価格 | 定価、割引、価格戦略など |
| Place | 流通 | 販売チャネル、店舗、配送方法など |
| Promotion | 販促 | 広告、SNS、イベント、PRなど |
✅ ポイント:「企業がどう売るか」を戦略的に整理するフレームワークです。
3.5F(ファイブ・フォース分析)
「競争環境分析」のためのフレームワーク
マイケル・ポーターが提唱したモデルで、業界の競争の強さ(儲かりやすさ)を分析します。
| 力(Force) | 内容 |
| 既存企業間の競争 | 同業他社との競争の激しさ |
| 新規参入の脅威 | 新しい会社が参入してくる可能性 |
| 代替品の脅威 | 他の手段や製品による代替の可能性(例:タクシー ⇔ Uber) |
| 買い手の交渉力 | 消費者や顧客が値下げを要求する力 |
| 売り手の交渉力 | 材料や部品を供給する側が持つ力(価格や条件など) |
✅ ポイント:新規事業の参入判断や業界の構造的な強さを知るために使います。
アクセス分析
77 77 とは、サイトにアクセスしてきた顧客の属性や行動を分析すること。
語群 1.WEB分析 2.デバイス分析 3.アクセス分析
✅ 正解:3.アクセス分析
🔹 アクセス分析とは?
「サイトにアクセスしてきた顧客の属性や行動を分析すること」を指します。
たとえば以下のようなことを調べます:
- どのページがよく見られているか
- ユーザーがどこから来たか(検索エンジン、SNS、他サイトなど)
- どの端末(PC、スマホ)を使っているか
- ページにどれくらい滞在したか
- コンバージョン(購入・登録など)につながったか
Googleアナリティクスなどのツールがよく使われます。
🔸 他の選択肢の説明
1.WEB分析(ウェブ分析)
「Web全体のデータを分析する広い概念」です。
アクセス分析もWEB分析の一部に含まれますが、他にも以下のような内容があります:
- 広告の効果測定
- コンテンツの評価
- SEO対策の成果確認
- ソーシャルメディアの反応分析 など
→「WEB分析」はより広いマーケティング全体を見渡す視点です。
2.デバイス分析
「ユーザーがどの**デバイス(端末)**を使っているかを分析すること」です。
- スマートフォン・タブレット・パソコンなどの種類
- OS(iOS, Android, Windowsなど)
- 画面サイズやブラウザの種類 など
→ サイトのデザインや広告配信を最適化するために使います。
まとめ
| 用語 | 意味 | 特徴 |
| アクセス分析 ✅ | サイトへの訪問者の行動を調べる | サイト改善に直結 |
| WEB分析 | ウェブ全体のマーケ分析 | 広い範囲をカバー |
| デバイス分析 | 使用端末の種類を分析 | デザイン・UXの最適化に使う |
ターゲティング
78 78 とは、市場を分析し、自社が扱う商品やサービスを「どのような顧客」に買ってもらう かを決めるプロセスのこと。
語群 1.ターゲティング 2.インサイト 3.スコアリング
✅ 正解:1.ターゲティング
🔹 ターゲティングとは?
「市場を分析し、自社が扱う商品やサービスを『どのような顧客』に買ってもらうかを決めるプロセス」です。
マーケティングでは、次の流れで進めます:
- セグメンテーション(市場を細かく分ける)
- ターゲティング(どの層を狙うか決める)
- ポジショニング(その層にどう印象づけるか)
たとえば:
- 若い女性向けにオシャレなカフェを展開する
- シニア層に使いやすいスマホを販売する
など、**「誰に向けて商品を売るか」**を明確にするのがターゲティングです。
🔸 他の選択肢の説明
2.インサイト(Insight)
「顧客自身も気づいていない、本音のニーズや感情」を指します。
マーケティングではとても重要なキーワードです。
例:
- 「安い」よりも「自分らしい」を重視する若者の価値観
- 忙しいママの「時間がないけど手を抜きたくない」という気持ち
→ インサイトをつかむことで、より心に響く商品や広告を作ることができます。
3.スコアリング
「顧客や見込み客の行動・属性に点数をつけて評価すること」です。
主に営業やマーケティングオートメーションで使われます。
例:
- メルマガを開いた → 10点
- 商品ページを3回見た → 30点
- 問い合わせフォームを送信 → 50点
→ 合計スコアが高い人を「今アプローチすべき顧客」と判断します。
まとめ
| 用語 | 意味 | ポイント |
| ターゲティング ✅ | 顧客層を絞って狙うこと | 誰に売るかを決める |
| インサイト | 潜在的な本音・感情 | 心に刺さる商品づくりに重要 |
| スコアリング | 顧客を点数で評価 | 優先度の高い顧客を見極める |
MA(マーケティング・オートメーション)
79 79 とは、ITを活用し、マーケティング業務のサポートや自動化をすることでマーケティ ングの効率化と生産性の向上などを実現させる仕組みのこと。
語群 1.IOT 2.RPA 3.MA
✅ 正解:3.MA(マーケティング・オートメーション)
🔹 MA(Marketing Automation)とは?
ITを活用して、マーケティング業務を自動化・効率化する仕組みです。
主な機能や活用例:
- メールの自動配信(例:誕生日クーポンを自動で送る)
- 見込み客のスコアリングと管理
- 顧客行動のトラッキング(どのページを見たか、何をクリックしたか)
- 顧客に合わせた内容の出し分け(パーソナライズ)
✅ 目的:マーケティング業務を「手作業から自動化」し、効率的に成果を出すこと。
🔸 他の選択肢の説明
1.IoT(Internet of Things)
「モノのインターネット」と呼ばれます。
- 家電、車、工場機械などのあらゆるモノがインターネットに接続されてデータをやりとりする技術です。
例:
- スマート冷蔵庫が食材の在庫を教えてくれる
- 工場の機械が異常を自動通知する
- ウェアラブルデバイスが健康情報を記録する
→ 主に「製造・インフラ・暮らし」分野で使われています。
2.RPA(Robotic Process Automation)
「定型的な業務をロボットに任せて自動化する技術」です。
マーケティングというより、事務作業・経理・人事などのバックオフィス業務に使われます。
例:
- Excelの転記作業を自動でやる
- メールの内容を読み取って、フォルダに振り分ける
- 会計ソフトにデータを自動入力する
✅ ポイント:人間のパソコン操作を真似してくれるのが特徴。
まとめ
| 用語 | 意味 | 主な用途 |
| MA ✅ | マーケティングの自動化 | 顧客管理・メール配信・効果分析など |
| IoT | モノのインターネット | 家電・車・工場のスマート化 |
| RPA | 業務の自動化ロボット | 定型作業の効率化(事務系中心) |
リテンション(Retention)
80 80 とは、顧客と関係を維持しながら継続的な利益確保を目指すマーケティング活動のこと。
語群 1.F2転換 2.1:5の法則 3.リテンション
✅ 正解:3.リテンション(Retention)
🔹 リテンションとは?
既存の顧客との関係を維持しながら、継続的に利益を生み出すマーケティング活動を指します。
つまり、「お客さんにずっとファンでいてもらうこと」が目的です。
💡 リテンション施策の例:
- 定期的なメルマガやクーポン配信
- 会員限定のポイント制度や特典
- 購入後のサポートやアフターサービス
- 誕生日や記念日のメッセージ送信
✅ ポイント:新規顧客を獲得するよりも、既存顧客を大切にする方がコストパフォーマンスが高いことが多いです。
🔸 他の選択肢の説明
1.F2転換(エフツーてんかん)
「初回購入者(First Buyer)をリピーター(Second Buyer)に転換させる」という意味です。
- 「F1=初回購入者」
- 「F2=2回目購入者(=リピーター)」
→ 初回購入だけで終わらせず、「もう一度買ってもらう」ことを目指すマーケティング戦略。
✅ F2に転換できれば、その後のリテンションにもつながります。
別解
F2転換とは?転換率の算出方法
F2転換とは、初回購入をした顧客が2回目のリピート購入をすることです。FはFrequency(頻度)のFで、3回目のリピート購入ならF3、4回目ならF4となります。
初回購入からF2転換に結びついた割合をF2転換率(リピーター率)と言います。マーケティング施策を実施したときの効果測定や、商品に対する顧客の満足度を知るときに役立ちます。F2転換率を算出するのは次の式を使います。
F2転換率(%)= 2回目のリピート購入をした顧客数 ÷ 初回購入顧客数 × 100例えば、初回購入顧客数3,000人のうち2回目購入が600人の場合、F2転換率は20%となります。
2.1:5の法則
マーケティングの有名な法則のひとつです。
「新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかる」
つまり、
- 新規顧客を集めるよりも、
- 既存顧客を大切にする方が効率的で利益も出やすい
✅ リテンション戦略の大切さを示す根拠としてよく使われます。
まとめ
| 用語 | 意味 | ポイント |
| リテンション ✅ | 顧客維持による利益確保 | 長期的な関係づくり |
| F2転換 | 初回購入者をリピーターに育てる | 購入回数UPの第一歩 |
| 1:5の法則 | 新規顧客の獲得は既存顧客維持の5倍コストがかかる | リテンションの重要性の裏付け |
まとめ
SC経営士の試験に教科書はありません。過去問はすべての受験生が勉強していますので、落とさないようにしてください。



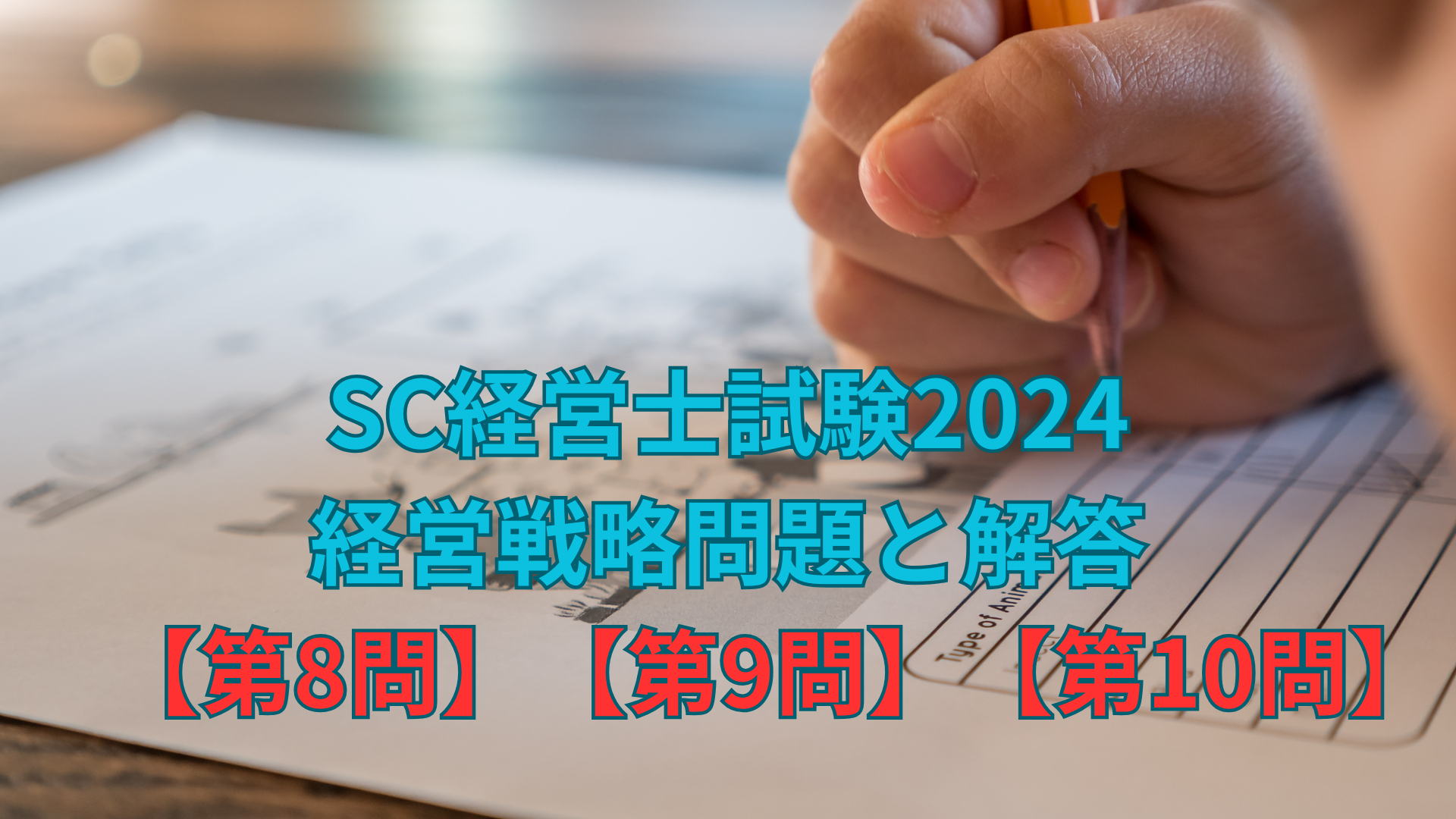


コメント