不燃ごみの種類や出し方を分かりやすく解説!
普段の生活で出るごみは「燃えるごみ」「資源ごみ」「不燃ごみ」などに分けて出しますよね。その中でも少し分かりにくいのが「不燃ごみ」。
今回は、不燃ごみの代表例と正しい出し方について、家庭向けに分かりやすく紹介します。
🔹 不燃ごみとは?
不燃ごみとは、燃やせない素材でできたものや、燃やすと有害物質が発生するものを指します。
ただし、分別のルールは自治体によって少しずつ違うので、あくまで一般的な例としてご覧ください。
🔹 不燃ごみの代表例
-
ガラス類:コップ、花瓶、ガラス皿、割れたガラスなど
-
陶磁器類:茶碗、お皿、植木鉢など
-
金属類:はさみ、フライパン、鍋、スプーンやフォークなど
-
小型家電(電池を抜いたもの):ドライヤー、電卓、懐中電灯など
-
その他:傘、蛍光灯、電球、化粧品のびん(中身を使い切ったもの)
🔹 出し方の基本ルール
-
指定袋に入れる
自治体指定の「不燃ごみ袋」に入れて出します。指定袋がない場合は透明または半透明の袋を利用します。 -
危険なものは工夫する
割れたガラスや刃物は新聞紙や厚紙で包み、「キケン」と書いてから袋に入れると収集員さんも安心です。 -
電池は別回収
乾電池やボタン電池は「有害ごみ」として別の回収ボックスへ。袋に入れてはいけません。 -
大型家電は対象外
テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどは「家電リサイクル法」の対象品。リサイクル回収や購入店に依頼しましょう。
🔹 出すときの注意点
-
袋の口はしっかり縛る
-
中身が分かるように透明袋を使用する
-
集積所には収集日の朝に出す(前日夜は禁止の地域も多い)
🔹 まとめ
不燃ごみは「燃やせないもの」「燃やすと危ないもの」と覚えておくと分かりやすいです。
ただし、実際の分別ルールはお住まいの自治体によって異なるため、必ず市区町村のホームページや配布されているごみ分別表をチェックしてください。
きちんと分別して出すことで、環境にもやさしく、安全に処理してもらえますよ😊

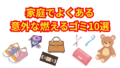

コメント