SC経営士試験2024経済一般問題と解答【第1問】【第2問】【第3問】【第4問】
解答1から20まで、問題、解答はSC協会のHPから作成しています。問題の最後に用語の意味も記載しています。略語にはいくつかの意味がありますので、ご自分でも調べてください。
https://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html
一部AIによる解説も入れていますが、参考程度にご利用ください。
国内総生産(GDP)
【第1問】〈配点 10点〉 (解答番号は 1 から 5 ) 次の国内総生産(GDP)に関する記述を読み、空欄に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、解答欄 にその番号をマークしなさい。
GDPとは、国内において、1年間に新たに生産された財と サービス の合計をいい、具体的な計算式は 民間消費+民間投資+民間在庫変動+政府支出+貿易収支(輸出-輸入) で表すことができる。 例えば、2023年の日本における物価変動影響考慮前の民間消費は約322兆円、民間投資は約122兆円、民間 在庫変動は約2兆円、政府支出は約154兆円、貿易収支は約9兆円の赤字であったが、その場合、GDPは約 591 兆円となる。また、GDPに占める民間消費の割合は約 54 %となる。 なお近年、日本は米国、中国に次いで世界第3位が定位置であったが、この2023年の物価変動影響考慮前の 名目 GDP(ドル換算)において、日本は ドイツ に抜かれ世界第4位となった。
語群( 1 〜 5 ) 1.CO2 2.サービス 3.利息 4.570 5.591 6.609 7.44 8.54 9.64 10.実質 11.中位 12.名目 13.インド 14.ドイツ 15.ブラジル
経済用語
【第2問】〈配点 10点〉 (解答番号は 6 から 10 ) 次の経済用語に関する記述を読み、記述文と最も関連の深い語句をそれぞれの語群から選び、解答欄にその 番号をマークしなさい。
家計金融資産
6 世帯が持つ現金・預金、株式などの総額を指し、日本銀行調査統計局が3カ月ごとに発表。2024年 3月末時点の金額は約2199兆円と過去最高額を更新している。
語群 6 1.家計金融資産 2.景気動向指数 3.商業動態統計 4.新設住宅着工戸数 5.家計消費支出
- 家計金融資産 (かけいきんゆうしさん)
家計金融資産は、個人や家庭が保有する金融的な資産のことを指します。これには現金、預金、株式、債券、保険契約、年金などの金融商品が含まれます。家計の財政状況や消費傾向を把握するために重要な指標となります。 - 景気動向指数 (けいきどうこうしすう)
景気動向指数は、経済の景気状況を把握するために、複数の経済指標を総合的に評価した指数です。これには生産、雇用、消費、投資など、経済の様々な側面が含まれます。景気が良い場合、指数は上昇し、景気が悪化している場合には下落することがあります。 - 商業動態統計 (しょうぎょうどうたいとうけい)
商業動態統計は、商業活動の動向を把握するために収集されるデータで、企業の売上高や店舗数、従業員数などを含みます。この統計は、小売業、卸売業、サービス業などの商業分野における経済活動の変化を測定するために使われます。 - 新設住宅着工戸数 (しんせつじゅうたくちゃっこうこすう)
新設住宅着工戸数は、新たに建設が始まった住宅の数を指します。この数は、住宅市場の動向や不動産業界の健全性を示す重要な指標であり、経済全体の需要や消費者の購買意欲とも関連しています。 - 家計消費支出 (かけいしょうひししゅつ)
家計消費支出は、家庭が生活に必要な商品やサービスを購入するために使う金額のことを指します。食費、住居費、光熱費、交通費、教育費など、生活に必要な支出全体が含まれ、消費動向を分析するために用いられます。
これらの用語は、経済や市場の状況を把握するための重要な指標として、様々な分析に利用されます。
消費者物価指数
7 消費者が購入する様々な商品価格の平均的な変動を測定した指数。総務省が毎月1回発表し、2022 年2月以降2024年6月までの月次伸び率は、日本銀行の物価安定目標の2%を超えている。
語群 7 1.鉱工業生産指数 2.国内企業物価指数 3.消費活動指数 4.消費者物価指数 5.日経商品指数
- 鉱工業生産指数 (こうこうぎょうせいさんしすう)
鉱工業生産指数は、鉱業や製造業、電力・ガス業などの産業における生産活動の動向を示す指数です。この指数は、一定期間内の生産量の変化を反映しており、経済の景気動向や生産能力の稼働状況を分析するために使用されます。 - 国内企業物価指数 (こくないきぎょうぶっかしすう)
国内企業物価指数は、日本国内で企業が取引する商品やサービスの価格動向を示す指数です。企業間での取引価格の変動を測定するもので、原材料や中間財などが含まれ、最終消費者物価とは異なり、企業間の取引段階での物価変動を反映します。 - 消費活動指数 (しょうひかつどうしすう)
消費活動指数は、消費者の購買行動や消費活動の状況を示す指標です。これには消費支出、消費者信頼感、販売高など、消費者の経済活動の変動を反映するデータが含まれ、経済全体の消費動向を把握するために用いられます。 - 消費者物価指数 (しょうひしゃぶっかしすう)
消費者物価指数は、消費者が購入する商品やサービスの価格の変動を示す指標です。消費者が日常的に購入する商品(食料品、住宅費、衣料品など)の価格変動を測定し、インフレ率やデフレ率を分析するための基本的な指標となります。 - 日経商品指数 (にっけいしょうひんしすう)
日経商品指数は、主要な商品(原材料や農産物など)の市場価格を反映した指数です。日本経済新聞社が算出しており、石油、金属、穀物などの価格動向を追うための指標となり、商品市場の動向を把握するのに利用されます。
これらの指数は、経済の状況を反映し、特に生産、物価、消費活動の変動を追跡するために重要な役割を果たします。
NISA
8 投資枠から得られた利益に対して税金が非課税になる制度の略称。2024年1月から内容が大幅に拡 充された。
語群 8 1.MMT 2.NDB 3.NISA 4.LTV 5.YCC
- MMT (現代貨幣理論, Modern Monetary Theory)
MMTは、政府が自国通貨を発行する限り、財政赤字や債務の拡大に対する制限がないという考え方に基づいた経済理論です。MMTによれば、政府は税金収入に依存せず、通貨発行を通じて経済を調整できるとされます。インフレを制御するためには、通貨の発行量を調整することが必要であり、財政支出を増やすことができる一方で、インフレ率が高くなれば発行を抑制することが求められます。 - NDB (新興開発銀行, New Development Bank)
NDBは、BRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)によって設立された国際開発銀行で、主に新興国や途上国のインフラ整備や経済開発を支援する目的で設立されました。この銀行は、開発途上国の持続的な成長を促進するために融資や投資を行っています。 - NISA (少額投資非課税制度, Nippon Individual Savings Account)
NISAは、日本における個人投資家向けの税制優遇制度です。NISAを利用すると、一定額の投資による利益(株式や投資信託など)の運用益に対して、通常かかる税金が免除されます。この制度は、個人投資家の資産形成を促進することを目的としています。 - LTV (Loan to Value, ローン・トゥ・バリュー比率)
LTVは、住宅ローンなどの融資において、借り手の不動産の評価額に対する借入金の比率を示す指標です。例えば、物件の評価額が1,000万円で、借入金が800万円の場合、LTVは80%となります。LTVが高いほど、金融機関にとってリスクが高いため、一般的に高LTVの融資には高い金利が設定されることが多いです。 - YCC (イールドカーブ・コントロール, Yield Curve Control)
YCCは、中央銀行が金利を特定の水準に誘導するための政策手段です。特に、日本銀行が採用している政策で、政府債券の金利(特に長期金利)の上限と下限を設定し、その範囲内に金利を収めるように市場を調整します。これにより、金利が過度に変動するのを防ぎ、経済を安定させることを目指します。
これらの用語は、金融政策や経済理論、投資関連の重要な概念です。
STO
9 電子的に発行された法令上の有価証券で資金調達を図る手法のひとつ。ブロックチェーンなどデ ジタル技術の活用により発行・管理コストの削減、証券の小口化や即時決済などが可能となる。
語群 9 1.DAO 2.ETF 3.J-REIT 4.STO 5.TOB
- DAO (分散型自律組織, Decentralized Autonomous Organization)
DAOは、ブロックチェーン技術を利用して運営される自律的な組織で、従来の中央集権的な管理者なしで、スマートコントラクトに基づいて意思決定が行われます。DAOのメンバーは、トークンを所有していることで意思決定に参加でき、投票によって組織の運営方針を決定します。この仕組みにより、透明性や分散性が高まり、中央集権的な権力の集中を避けることができます。 - ETF (上場投資信託, Exchange-Traded Fund)
ETFは、株式のように取引所で売買される投資信託です。通常、株式や債券、商品、インデックスなどの特定の資産クラスを追跡し、投資家はその成績に応じたリターンを得ることができます。ETFは流動性が高く、売買手数料が比較的低いことから、個人投資家に人気があります。 - J-REIT (日本版不動産投資信託, Japan Real Estate Investment Trust)
J-REITは、日本国内の不動産に投資する上場投資信託です。個人投資家は、J-REITを通じて不動産市場に間接的に投資することができ、安定した収益を期待することができます。J-REITは、商業施設やオフィスビル、住宅、物流施設など、さまざまな不動産に分散投資することが特徴です。 - STO (セキュリティ・トークン・オファリング, Security Token Offering)
STOは、ブロックチェーン技術を用いて発行される証券型のトークンを投資家に販売する資金調達手法です。STOは、従来の株式や債券と同様に法的な規制を受けるため、ICO(Initial Coin Offering)とは異なり、投資家保護が強化されています。STOを通じて発行されるトークンは、投資家に利益配分や権利を与える証券としての性質を持ちます。 - TOB (株式公開買付け, Takeover Bid)
TOBは、企業が他の企業の株式を公開市場で買い付け、支配権を取得するための手法です。TOBは、買収対象企業の株主に対して一定の価格で株式を買い取ることを提案するもので、買収のための競争入札の形を取ることもあります。企業買収や合併の際に頻繁に用いられ、敵対的な買収などにも利用されることがあります。
これらの用語は、投資や企業買収、資金調達に関連した重要な概念です。
VIX
10 米国の株価の先行きについて、投資家が見込んでいる変動幅(ボラティリティー)に関する指数。 「恐怖指数」とも呼ばれ、この指数が20を超えると強い警戒感を示すとされる。
語群 10 1.CDX 2.FX 3.SCB 4.VC 5.VIX
- CDX (クレジット・デフォルト・スワップ・インデックス, Credit Default Swap Index)
CDXは、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)契約のインデックスで、特定の債務者グループ(企業や国など)の信用リスクを反映するものです。投資家は、CDXを利用して複数の債務者のデフォルトリスクを取引することができ、信用市場全体の動向を反映する指標としても使われます。CDXは、信用リスクのヘッジや投機に用いられます。 - FX (外国為替, Foreign Exchange)
FXは、外国為替市場での通貨の売買を指します。通常、通貨ペア(例えば、USD/JPYなど)で取引され、為替レートの変動を利用して利益を得ることを目的としています。FX市場は世界最大の金融市場であり、個人や機関投資家が24時間取引を行っています。 - SCB (スタンダード・チャータード銀行, Standard Chartered Bank)
SCBは、イギリス・ロンドンを本拠地とする国際的な商業銀行です。アジア、中東、アフリカを中心に広がるグローバルなネットワークを持ち、法人向けの銀行業務や投資銀行業務を提供しています。個人向けにも銀行サービスを提供し、特に新興市場に強みを持っています。 - VC (ベンチャーキャピタル, Venture Capital)
VCは、成長が期待される初期段階の企業(スタートアップ)に対して資金を提供する投資活動を指します。ベンチャーキャピタルは、リスクを取って投資を行う代わりに、高いリターンを期待します。投資先企業の成長に伴って、株式公開(IPO)や企業売却(M&A)などの手段で利益を得ることが一般的です。 - VIX (ボラティリティ・インデックス, Volatility Index)
VIXは、米国株式市場における30日間の予想ボラティリティを示す指数です。通称「恐怖指数」とも呼ばれ、S&P 500指数のオプション価格を元に算出されます。VIXが高いと、株式市場の不安定さやリスクが高まっていることを意味し、逆にVIXが低いと市場の安定性が高いと解釈されます。投資家やトレーダーが市場の先行きに対する不安を感じているかどうかを示す指標として広く利用されています。
これらの用語は、金融市場、投資、リスク管理に関連する重要な概念です。
財務省が公表した「国の財務書類」
【第3問】〈配点 10点〉 (解答番号は 11 から 15 ) 次の文章および図表は、2024年3月26日に財務省が公表した「国の財務書類」に関する記述である。空欄に入 る最も適切な語句を下記の語群から選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 国の財務書類は、国全体の資産や負債などの ストック の状況、費用や財源などのフローの状況といった 財務状況を一覧でわかりやすく開示する観点から、企業会計の考え方および手法(発生主義、複式簿記)を 参考として、平成15年度決算分より財務省が作成・公表している。 そのうち、以下の図表は、公表資料に基づいた2023年3月31日時点における連結貸借対照表である。
この図表において、負債合計額は約 1545 兆円である。一方、企業会計の純資産に該当する、資産か ら負債を差し引いた差額は約 582 兆円のマイナスである。したがって、企業会計における 債務超過 の状態にはあるが、その金額の絶対値は2023年のGDPの金額を若干下回る程度であるともいえ る。但し、国の保有する財産は 国会議事堂 に代表されるように、賃料収入が見込めず売却して換金することが容易ではない財産も多く含まれていることには留意が必要である。
語群( 11 〜 15 ) 1.ストック 2.サプライ 3.デマンド 4.1045 5.1245 6.1545 7.562 8.582 9.602 10.債務超過 11.資産超過 12.不良債権 13.国会議事堂 14.東京タワー 15.横浜アリーナ
- ストック(Stock)
ある時点での蓄積量を指す言葉で、たとえば「資産ストック」は企業や家計が保有するお金や財産などの総量を意味します。対義語は「フロー(Flow)」で、一定期間に発生する変化量を表します。 - サプライ(Supply)
「供給」の意味です。経済学では、商品やサービスを市場に提供することを指し、価格が高いほど供給量は増える傾向にあります。 - デマンド(Demand)
「需要」の意味で、商品やサービスを買いたいという消費者の欲求を表します。価格が安いほど、一般的に需要は増加します。 - 債務超過(さいむちょうか)
企業などが保有する資産よりも負債の方が多く、純資産がマイナスになっている状態です。財務的に危機的状況で、倒産リスクが高まります。 - 資産超過(しさんちょうか)
債務超過の逆で、資産が負債よりも多く、純資産がプラスである健全な財務状態です。企業の信用力が高く、健全経営の指標とされます。 - 不良債権(ふりょうさいけん)
回収の見込みが低い貸付金などを指します。銀行や金融機関が貸したお金が返済されない、あるいは遅延しているような場合に分類されます。 - 国会議事堂(こっかいぎじどう)
東京都千代田区にある、日本の立法府「国会」が開かれる建物です。衆議院と参議院の本会議場や委員会室などが設けられています。 - 東京タワー(とうきょうタワー)
東京都港区にある、高さ333メートルの電波塔で、1958年に完成しました。観光名所としても有名で、展望台からは東京全体を一望できます。 - 横浜アリーナ(よこはまアリーナ)
神奈川県横浜市にある大型の多目的ホール・アリーナです。音楽ライブ、スポーツイベント、式典など多くのイベントに利用される施設です。
“超”人手不足時代に『効く』対策を求めて
【第4問】〈配点 5点〉 (解答番号は 16 から 20 ) 『SC JAPAN TODAY』2023年11月号特集「“超”人手不足時代に『効く』対策を求めて」の掲載 記事に関連する次の記述のうち正しいものには1を、誤っているものには2を、解答欄にマークしなさい。
副業・兼業に関するアンケート調査結果
16 2022年10月に(一社)日本経済団体連合会が公表した「副業・兼業に関するアンケート調査結果」 によると、自社社員に社外での副業・兼業を「認めている」「認める予定」との回答をした企業は 約6割程度である。
2
副業・兼業に関するアンケート調査結果2022年10月に(一社)日本経済団体連合会が公表した「副業・兼業に関するアンケート調査結果」によると、自社社員に社外での副業・兼業を「認めている」「認める予定」との回答をした企業は約6割程度である。
→ 回答:2(誤り)
解説:
実際には「認めている」「認める予定」と回答した企業は**約5割程度(正確には49.6%)**であり、6割には達していません。このため、「約6割」という記述は誤りです。
副業・兼業
17 副業・兼業において大きな留意点となるのは労働時間管理、特に労働時間の通算であるが、これに 関しては厚生労働省から「管理モデル」が提示されている。
1
副業・兼業において大きな留意点となるのは労働時間管理、特に労働時間の通算であるが、これに関しては厚生労働省から「管理モデル」が提示されている。
→ 回答:1(正しい)
解説:
副業・兼業において、複数の雇用先の労働時間を通算する必要がある場合、過重労働や法定労働時間超過のリスクがあります。そのため、**厚生労働省は「副業・兼業の労働時間管理モデル」**を公表しており、これを参考に企業が適切な管理を行うことが推奨されています。
18 副業・兼業を禁止したり、一律許可制にしたりしている場合には就業規則を見直す必要があるが、 この就業規則に関する明確なモデルは現状においては存在しない。
2
副業・兼業を禁止したり、一律許可制にしたりしている場合には就業規則を見直す必要があるが、この就業規則に関する明確なモデルは現状においては存在しない。
→ 回答:2(誤り)
解説:
実際には、厚生労働省が副業・兼業の就業規則モデルを示しており、企業が参考にできるガイドラインとして整備されています。そのため、「明確なモデルが存在しない」というのは誤りです。
外国人雇用状況
19 労働施策総合推進法28条1項に基づき外国人雇用状況の届出が提出されている人数は、2023年10月 末時点においては200万人を超えている。
1
労働施策総合推進法28条1項に基づき外国人雇用状況の届出が提出されている人数は、2023年10月末時点においては200万人を超えている。
→ 回答:1(正しい)
解説:
厚生労働省の発表によると、2023年10月末時点での外国人労働者数は約204万人で、実際に200万人を超えています。これは過去最多の人数となっています。
外国人雇用
20 外国人雇用に関して2019年に創設された、現場での就労のための制度である特定技能制度のうち、 SCの営業・運営に関連する特定技能の対象業種は、現時点で「ビルクリーニング業」と「外食業」 のみであり、「販売業(職)」は対象外である。
1
外国人雇用に関して2019年に創設された、現場での就労のための制度である特定技能制度のうち、SCの営業・運営に関連する特定技能の対象業種は、現時点で「ビルクリーニング業」と「外食業」のみであり、「販売業(職)」は対象外である。
→ 回答:1(正しい)
解説:
「特定技能」制度において、SC(ショッピングセンター)に関連しそうな業種のうち、対象となっているのは**「ビルクリーニング業」と「外食業」**です。一方で、「販売業(職)」は現在のところ特定技能の対象業種には含まれていません。したがって記述は正しいです。
まとめ
SC経営士の試験に教科書はありません。過去問はすべての受験生が勉強していますので、落とさないようにしてください。
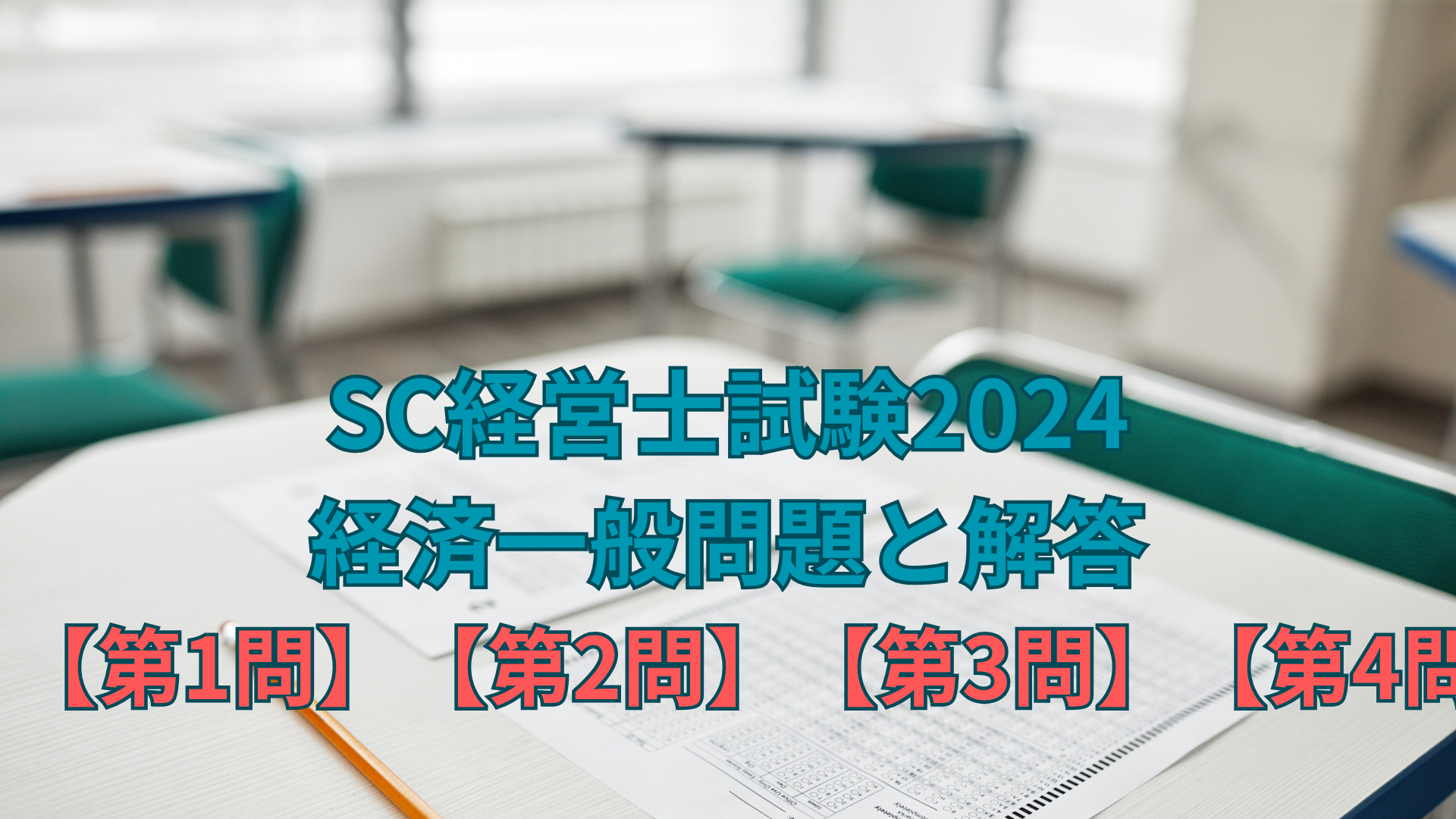

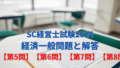
コメント